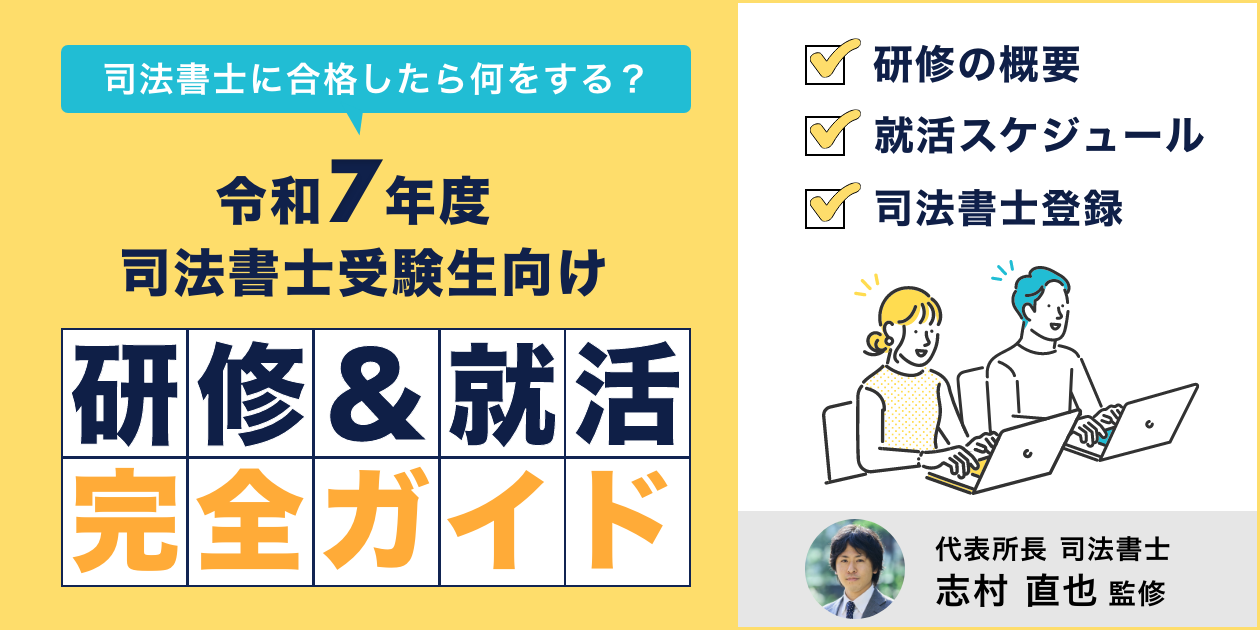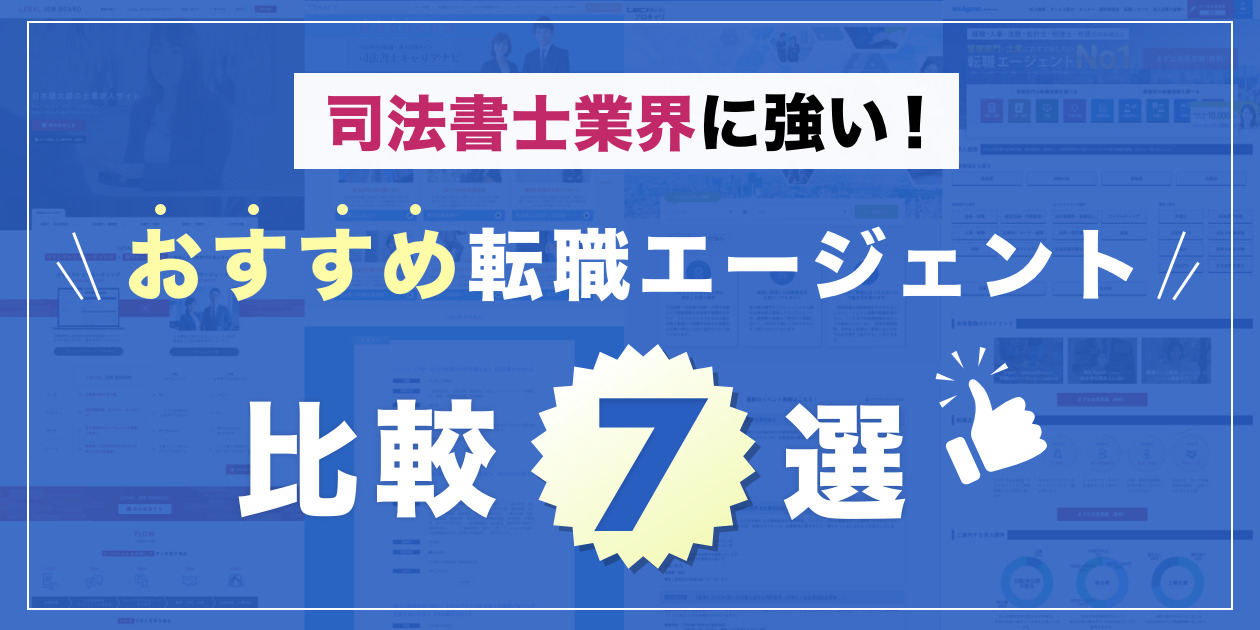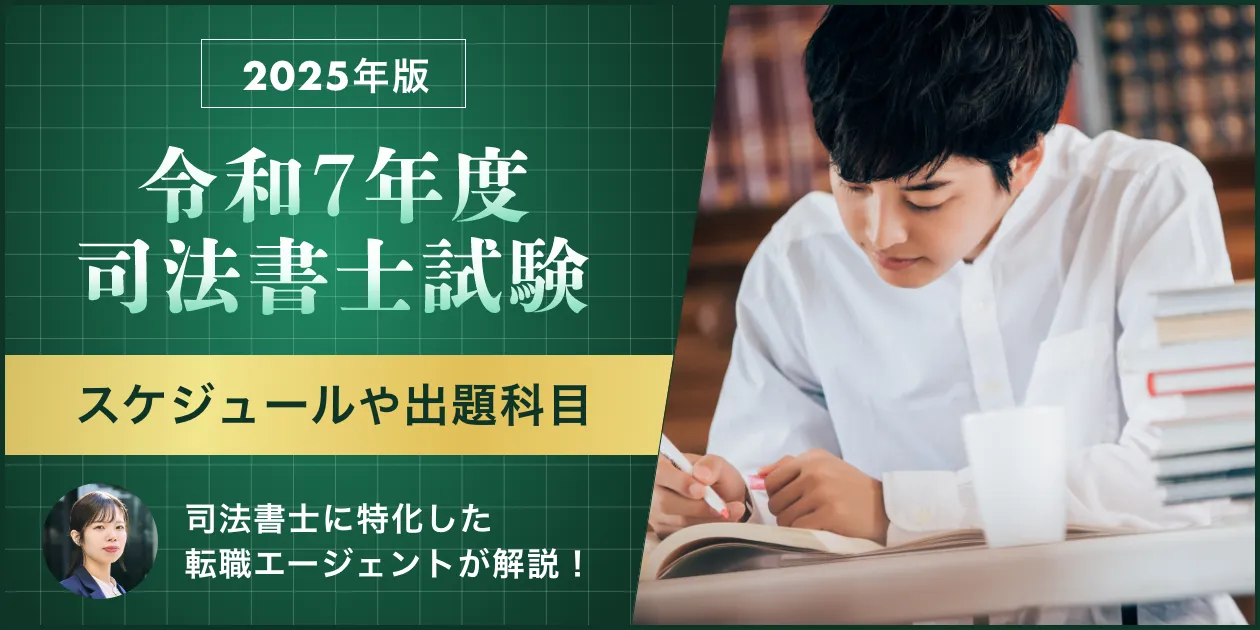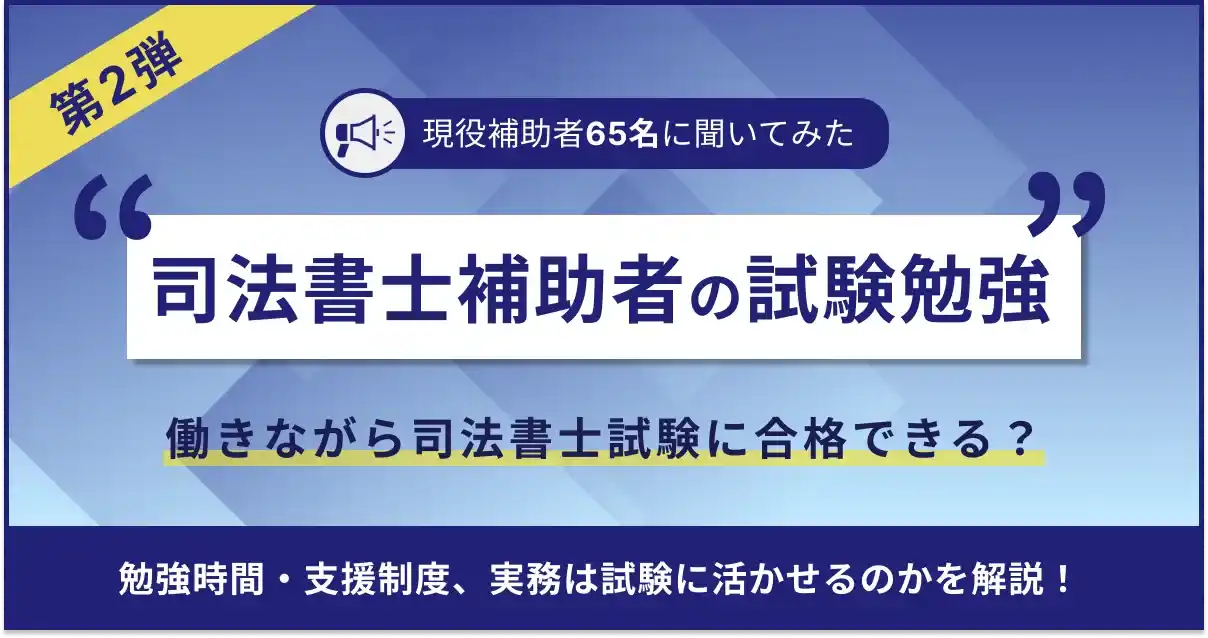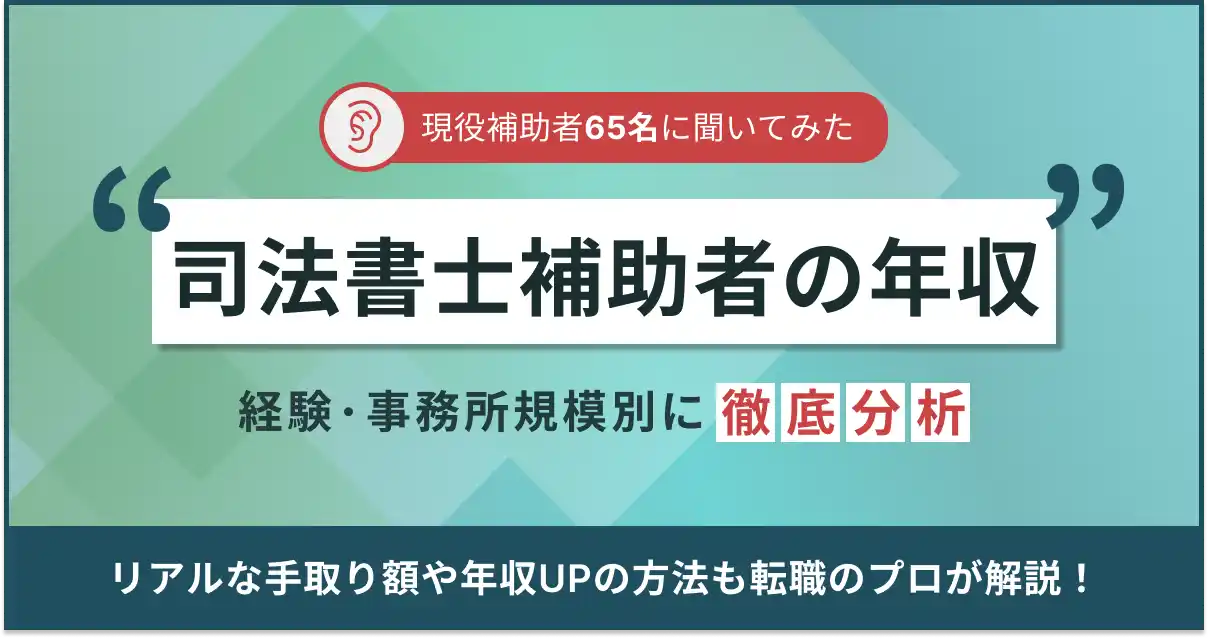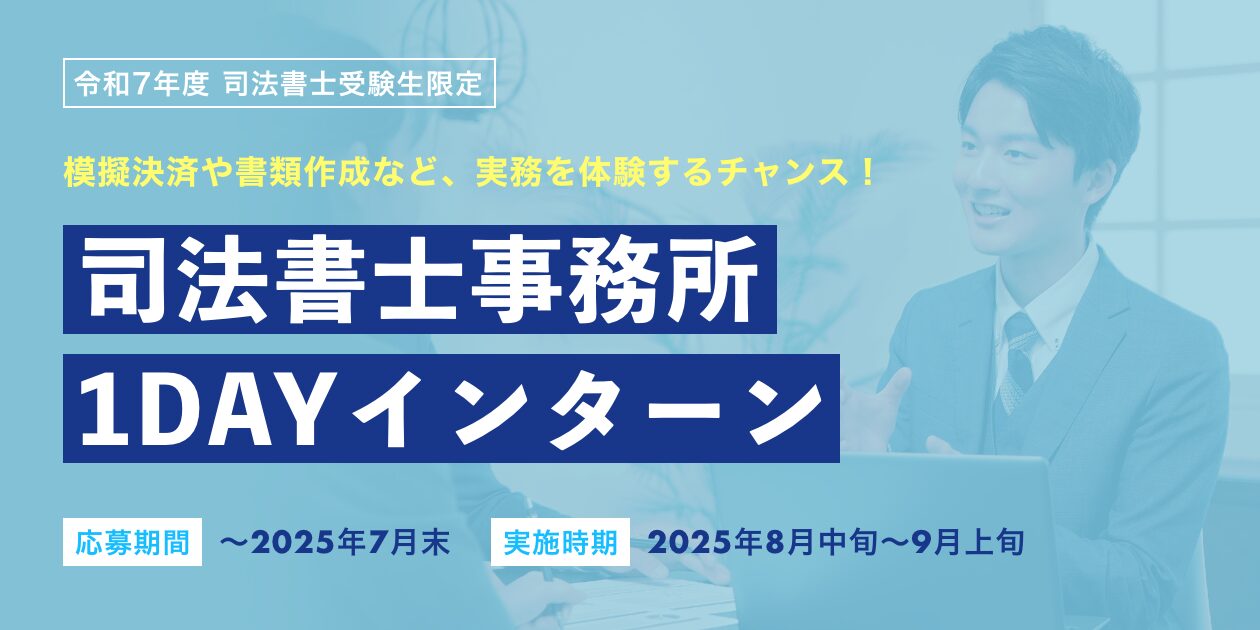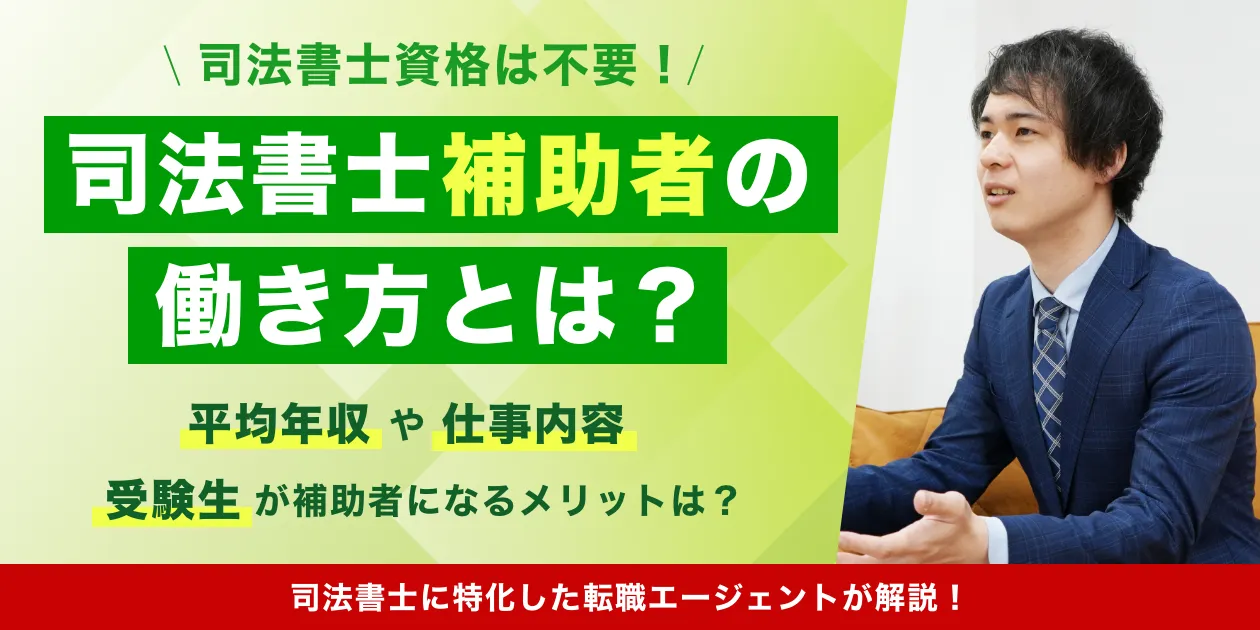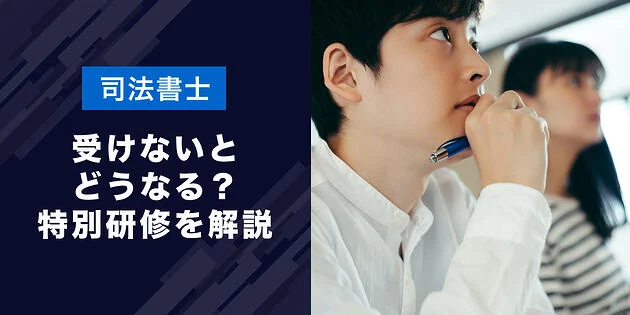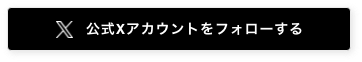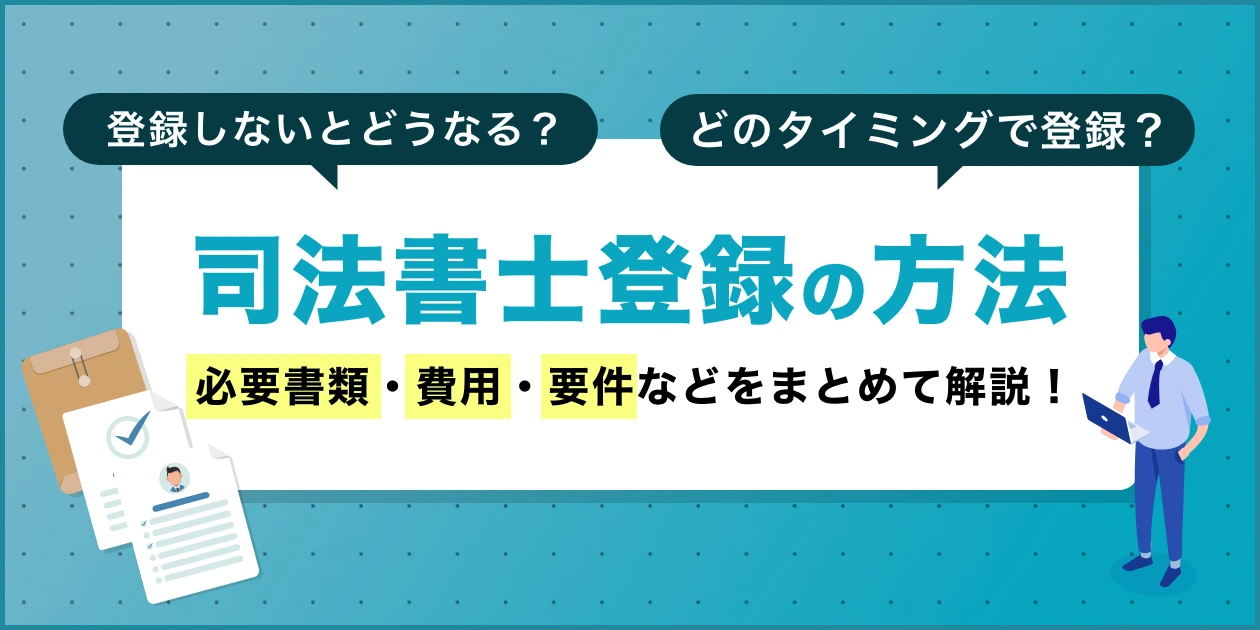
【司法書士登録】手続きや登録料・必要書類を詳しく解説!登録しないとどうなる?

by LEGAL JOB BOARD 小山
キャリアアドバイザー
- 担当職種:
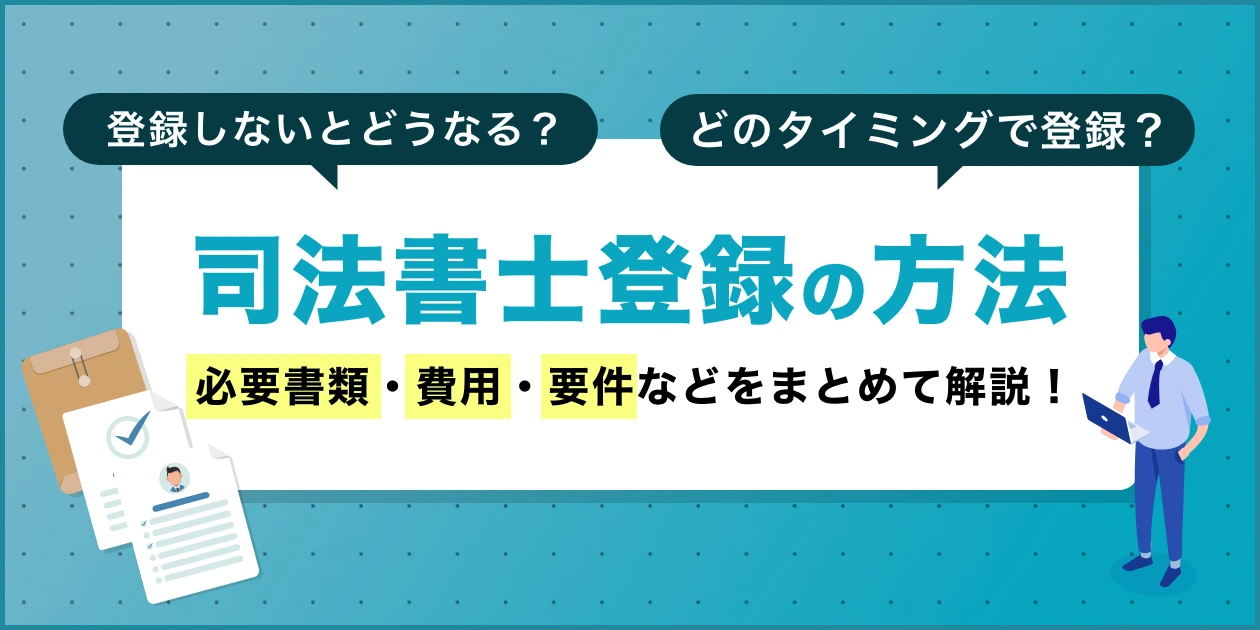
この記事の目次
司法書士登録の流れ
司法書士として働きたい方は、必ず司法書士登録を行わなくてはなりません。これは、司法書士法第8条の規定によって定められています。
司法書士登録までの主なステップは以下の通りです。
- 司法書士試験に合格
- 新人研修を受講
- 日本司法書士連合会に登録申請(各司法書士会を経由して登録申請書を提出)
まず、司法書士試験に合格することは必須条件です。その後、ほとんどの合格者の方が、新人研修を受講してから司法書士登録を行います。
司法書士の登録要件
前述の内容と重複しますが、司法書士試験に合格しないと登録は行えません。
試験合格後には、新人研修を受講します。新人研修とは、中央新人研修・ブロック新人研修・司法書士会新人研修(配属研修)のことで、日本司法書士連合会・司法書士会に「1年以内に登録・入会予定の方」が対象です。
新人研修は未受講・未修了でも登録可能ですが、その場合、原則1年以内に新人研修を受講する必要があります。また、入会する司法書士会によっては、原則すべての研修を受講しないと登録できないケースも。
登録要件の詳細については、入会を希望する司法書士会の情報を収集し、不明点があれば問い合わせることをおすすめします。
あわせて読みたい記事
「司法書士としての就職・転職について相談したい」「働き方や今後のキャリアについて考えたい」といった方は、リーガルジョブボードの司法書士専門キャリアアドバイザーまで、お気軽にご相談ください。
司法書士登録の費用(登録料)
司法書士登録にかかる費用は、以下の通りです。
- 登録手数料:25,000円
- 登録免許税:30,000円
- 司法書士会の入会金:35,000円~50,000円前後(各司法書士会による)
- 司法書士会の定額会費
- バッジ代:6,500円前後
登録後、司法書士として司法書士事務所に勤務する場合、登録にかかる費用を全額負担してもらえる可能性が高いです。ただし、事務所によっては、短期離職すると費用の返還を求められることもあります。
定額会費についても、多くの司法書士事務所では負担してもらえるでしょう。
仮に東京司法書士会に入会するならば、入会金は35,000円、定額会費は月額17,200円です。大阪司法書士会であれば、入会金は40,000円、定額会費は月額17,000円です。
登録方法・必要書類
司法書士登録にあたっては、入会する司法書士会に必要書類を提出します。司法書士登録申請書は、司法書士会を経由して連合会に提出されます。
主に必要になる書類は以下の通りです。必要書類や様式などは、各司法書士会によって異なりますのでご注意ください。
- 登録申請書(登録免許税の収入印紙を貼付)
- 司法書士となる資格を有することを証する書面
- 司法書士名簿(顔写真を貼付)
- 住民票の写し
- 身分証明書(成年被後見人・被保佐人・破産者でないことの証明)
- 登記されていないことの証明書(成年被後見人や被保佐人でないことの証明)
- 入会届(職印を押す必要あり)
- 誓約書
- 履歴書
- 簡裁訴訟代理等能力認定考査の認定証書(※該当者のみ)
書類をそろえる以外にも、顔写真や職印の準備、登録免許税の納付が必要になります。余裕を持って準備を進めましょう。
詳しくは各司法書士会のHP等で情報を確認してください。同じ司法書士会に入会している先輩・同期の司法書士に聞いてみるのも良いかもしれません。
「司法書士としての就職・転職について相談したい」「働き方や今後のキャリアについて考えたい」といった方は、リーガルジョブボードの司法書士専門キャリアアドバイザーまで、お気軽にご相談ください。
登録のタイミングは?
司法書士登録のタイミングは、個人によって異なります。年度ごとに申請期間や締切が設けられているといったこともありません。
ただ、司法書士事務所・法人に勤務する場合は、勤務先の意向や判断で登録時期が決まる傾向にあります。リーガルジョブボードで就職支援を行った司法書士の方々も、登録のタイミングは勤務先によって様々です。
入職日に登録手続をする方もいれば、入職から1年後に登録する方も。後者の方は、勤務先が「司法書士業務を一人前にできるようになってから登録して欲しい」という意向だったため、1年後の登録となりました。
また、登録費用や定額会費を勤務先が負担する場合は、費用面の事情も登録のタイミングに関係するかもしれません。司法書士登録を行う予定の方は、登録費用・会費を負担してもらえるのか、登録時期の目安はどれくらいなのか、就職前に確認しておくのがおすすめです。
司法書士登録をしないとどうなる?
司法書士登録をしなければ、司法書士として働くことはできません。当然ながら、不動産登記や商業登記の申請代理といった独占業務も、登録なしに行うことはできません。そのため、司法書士として働きたい方は登録が必須です。
一方で、試験合格後に司法書士として働かない方は、特に登録を行う必要はないでしょう。司法書士には試験合格後の登録期限もないため、もし司法書士として働きたくなった場合は、何年後であっても登録を検討することが可能です。
登録を行うメリット・デメリット
司法書士登録のメリット・デメリットをご紹介します。
メリット
司法書士登録をする最大のメリットは、司法書士として働けることです。
不動産登記・商業登記の申請代理といった司法書士の独占業務は、司法書士登録をしていないと行うことができません。
また、登録していることで、司法書士会が開催する研修会に参加できます。この研修会は、法改正に対応した知識を得る機会や、業務に必要な知識を学ぶ機会として活用できるでしょう。
デメリット
強いて言うならば、登録・入会などに費用がかかる点です。
司法書士試験の合格後は、新人研修や司法書士登録など、まとまった出費がいくつか発生します。また、登録後も継続して会費を支払う必要があります。しかし、前述の通り、多くの司法書士事務所では登録費用・会費ともに負担してもらうことができます。
また、司法書士の独占業務が行えることや、司法書士として働き続けられることを考慮すれば、登録のデメリットよりもメリットの方が遥かに大きいのではないでしょうか。
司法書士の求人はこちら
司法書士専門の求人サイト「リーガルジョブボード」には、司法書士の求人が豊富に掲載されています。未経験の方、合格者の方向けの求人も取り揃えていますので、ぜひ一度ご覧ください。
【新着】司法書士の求人一覧
ちなみに、司法書士業界に特化した転職キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」では、あなたのご希望条件(エリア・年収・残業時間など)に合った司法書士求人を随時ご紹介しております。
紹介する求人には、サイト上でご覧いただけない非公開求人も含まれており、より多くの求人を知ることができます。
また、キャリアアドバイザーが求人選定や面接調整、書類添削など包括的にサポートさせていただきますので、なかなか転職活動のお時間が取れない方にもおすすめです。
あわせて読みたい記事
▼リーガルジョブマガジンとは
司法書士の転職・キャリアに関するお役立ち情報や、業界知識・動向、インタビュー記事などを発信するメディアです。
記事一覧を見る