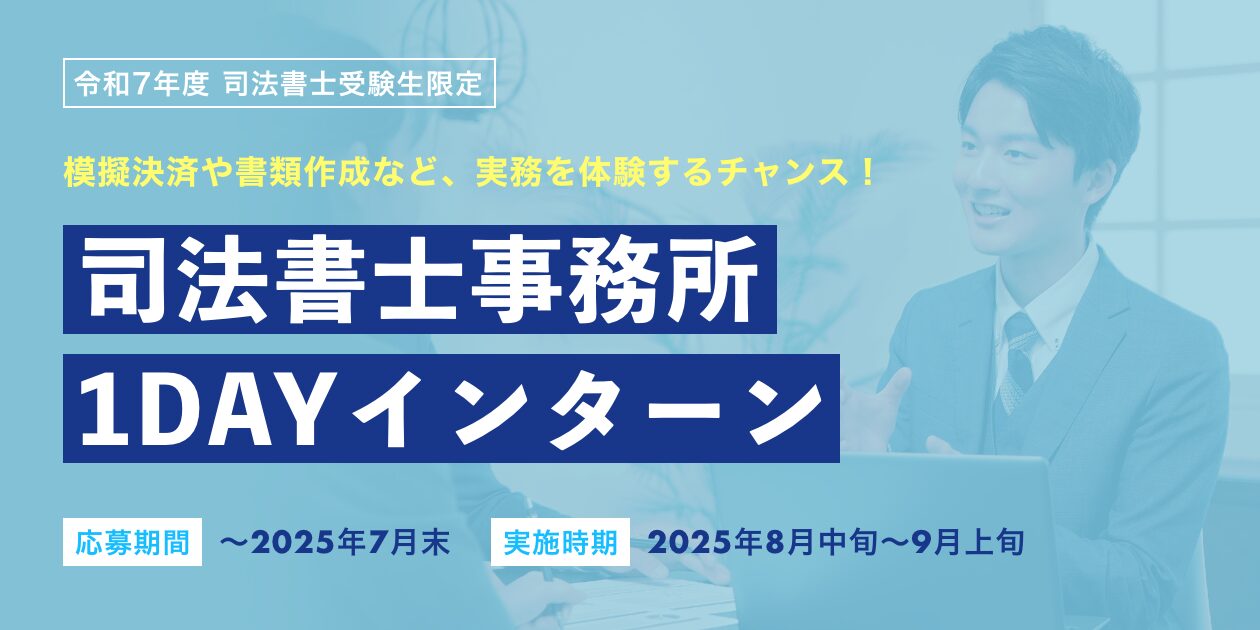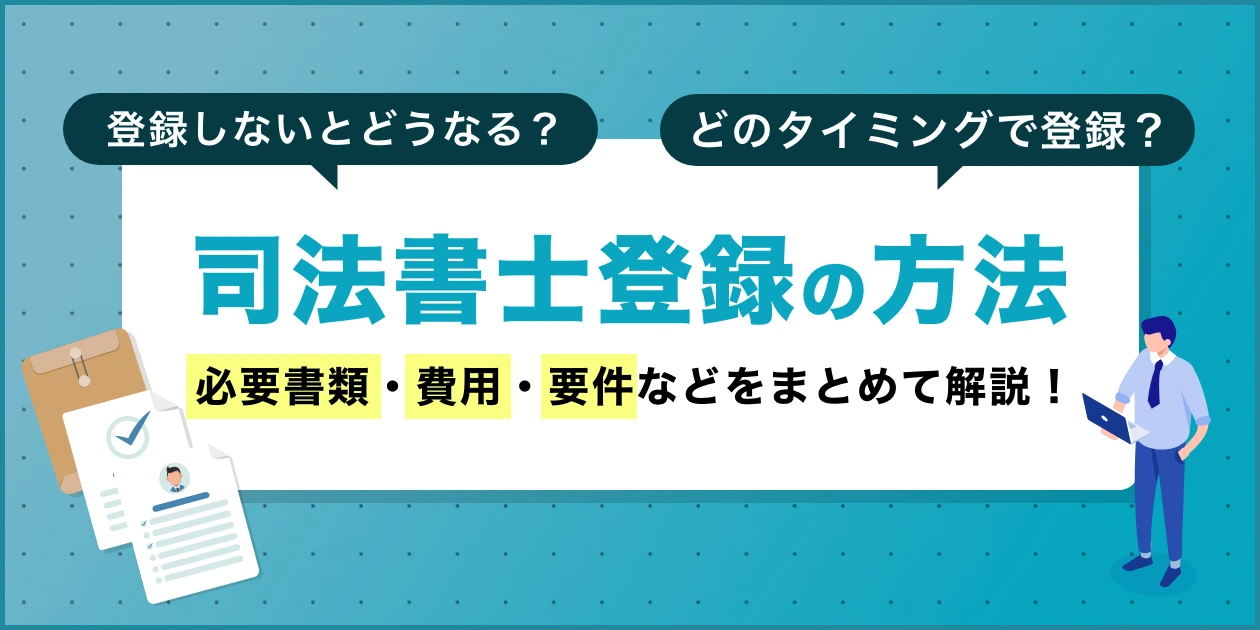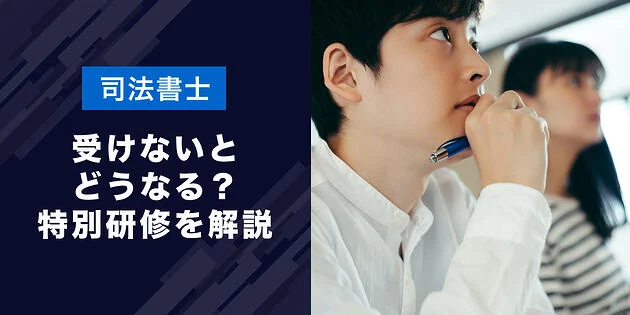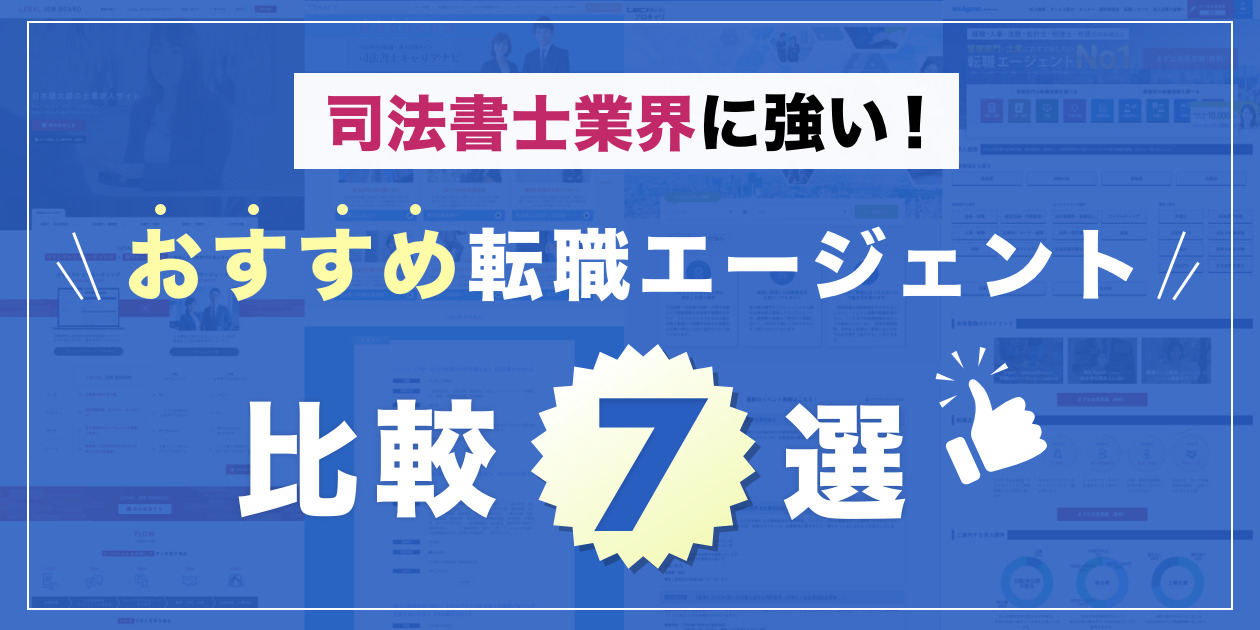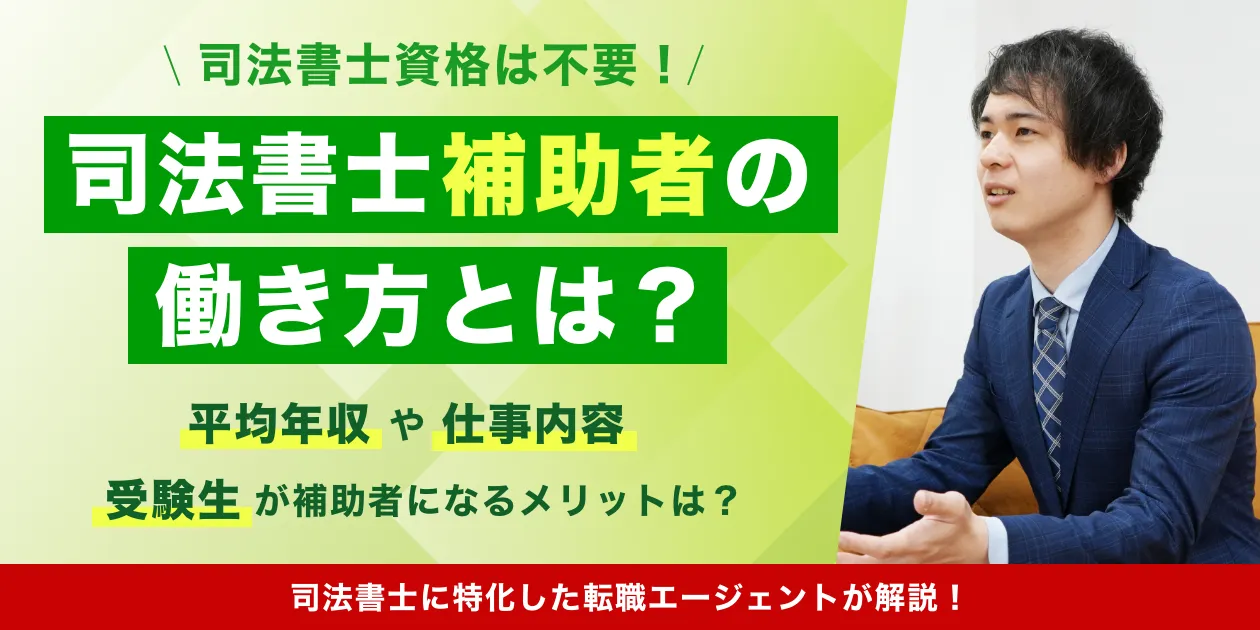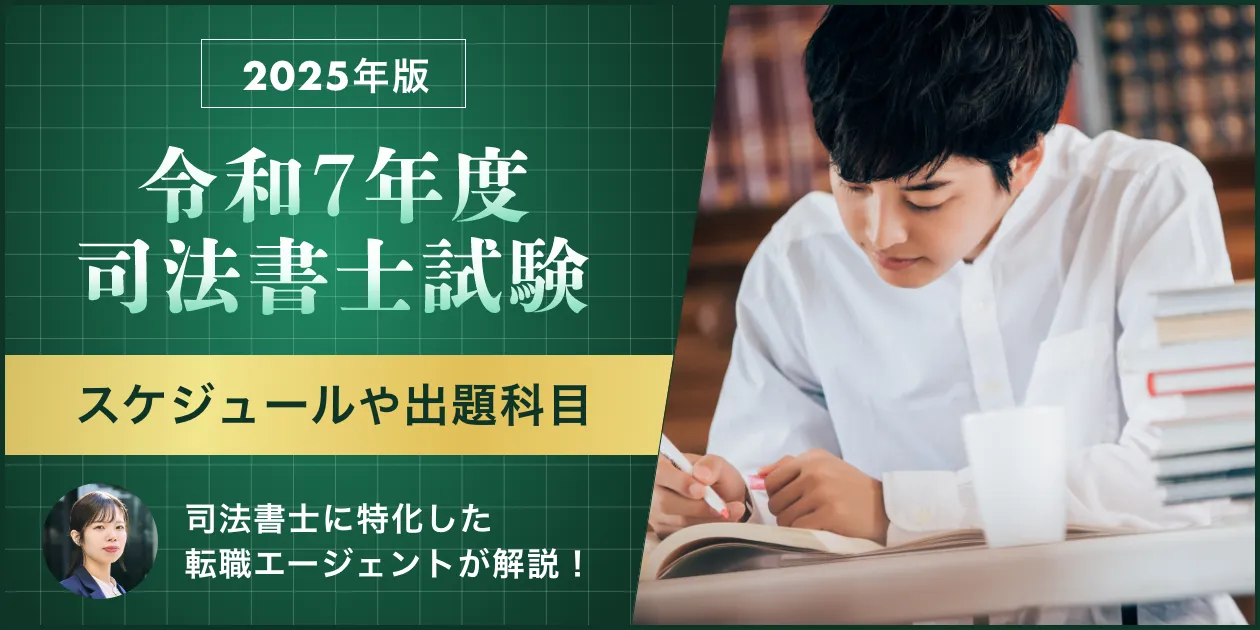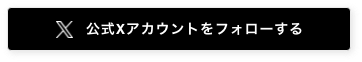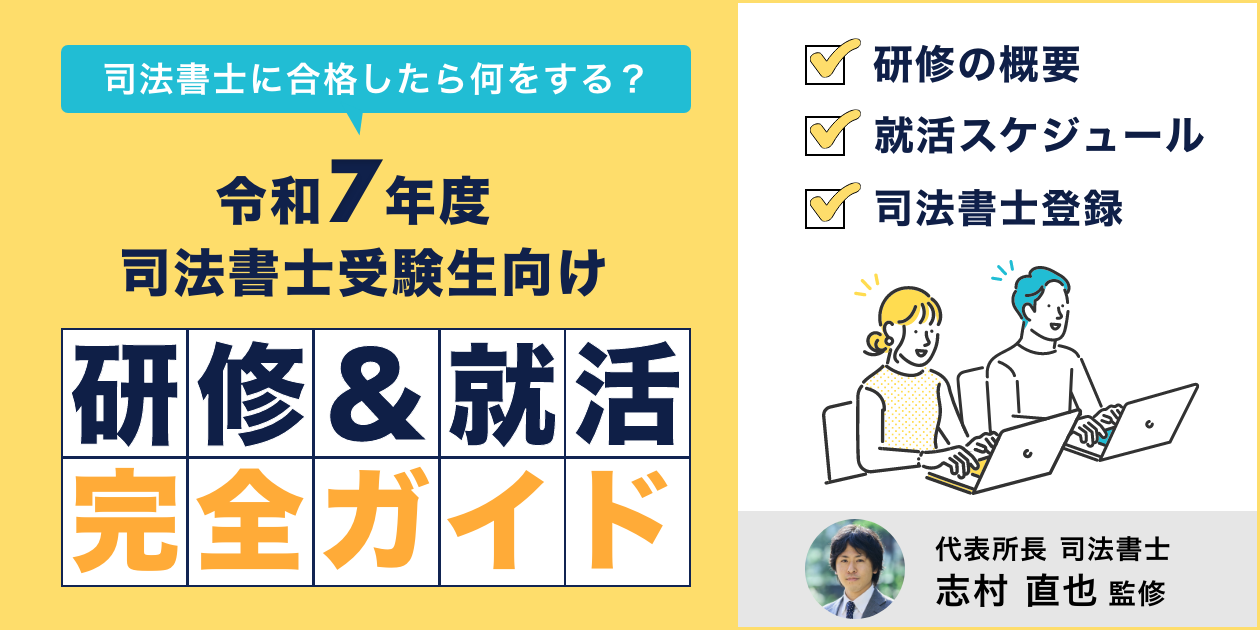
令和7年度|司法書士合格後の新人研修・就職活動・登録などを詳しく解説

by LEGAL JOB BOARD 北澤
キャリアアドバイザー
- 担当職種:
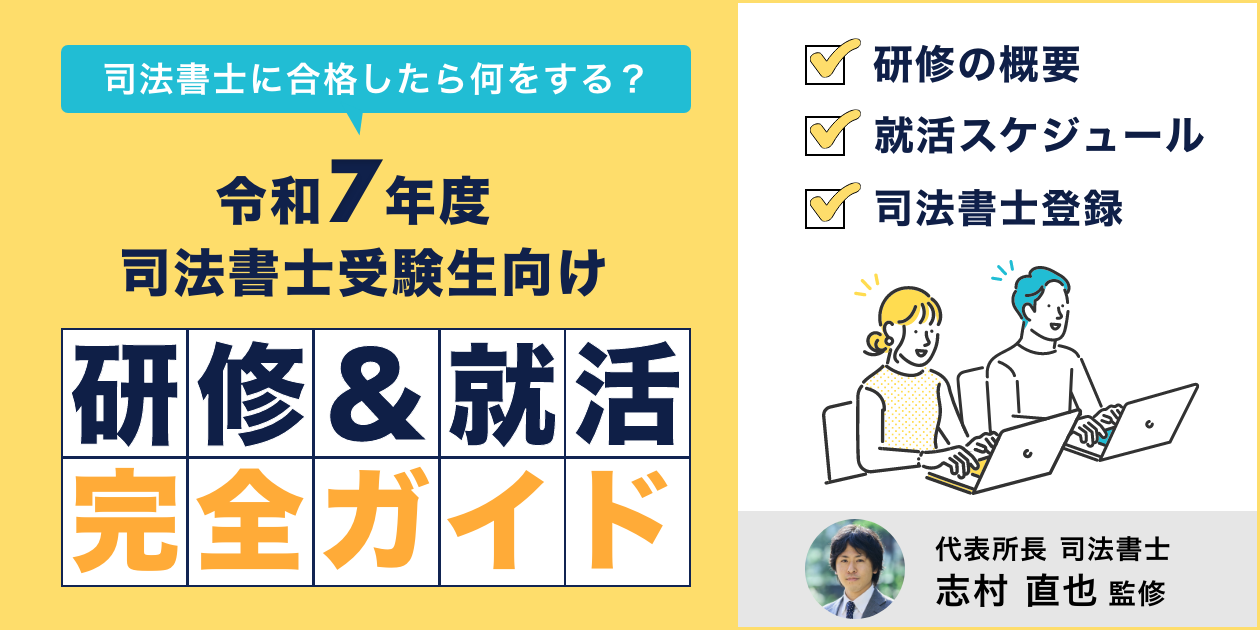
司法書士に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の北澤です。
本記事では、「令和7年度版|司法書士試験の合格後にやるべきこと」として、
などについて網羅的に解説します。
令和7年度 司法書士試験を受験される方や、司法書士の就職活動について知りたい方は、ぜひ参考になさってください。
あわせて読みたい記事
この記事の目次

この記事の監修者
フラタニティ司法書士事務所 代表司法書士
志村直也 氏
司法書士試験の合格後にやるべきことは?
司法書士試験に合格後は、新人研修を受けて司法書士登録をしたり、司法書士としての就職・転職活動を行ったりする必要があります。具体的には以下の通りです。
- 司法書士として就職・転職活動をする
- 新人研修を受ける
- 司法書士登録を行う(※多くの方は就職後)
- 特別研修・認定考査を受ける
司法書士としての就職・転職活動は、基準点発表や筆記試験の合格発表を機に動き出す方が多いです。
また、特別研修と認定考査は「認定司法書士」になるために必要であり、必須ではありません。
司法書士としての就職・転職活動はいつから始める?
令和7年度 司法書士試験を受験する方の就職活動スケジュールは、
- 合格見込みのうちに動き始める(最もおすすめ)
- 11月5日の合格発表後に最短で動く
- 新人研修後から動き始める
の3パターンがあります。
詳しいスケジュールをはじめ、司法書士の就職活動に関する情報は以下の記事で解説しています。ぜひご覧ください。
あわせて読みたい記事
令和7年度 司法書士試験 受験生の方向けのイベント情報
司法書士の新人研修とは?
司法書士の新人研修とは、「中央新人研修」「ブロック新人研修」「各司法書士会 新人研修」の3つを指します。
合格後1年以内に日本司法書士会連合会に名簿登録し、司法書士会に入会する場合、新人研修の受講が推奨されています(※都道府県ごとの司法書士会により規定が異なります)。
研修の期間は、最終合格発表後の12月から翌年3月までの約4ヵ月です。細かい研修日程は、籍をおく司法書士会によって異なります。
3つの研修それぞれの内容や日程などの詳細を以下で説明します。
中央新人研修の日程・内容
中央新人研修は、PCやスマートフォンで受講できる“eラーニング研修”で、期間内に全て受講した上、動画内で出てくる確認問題に正解することで修了となります。
視聴グループは、ブロック新人研修の受講会場に応じて決定され、選択することはできません。
研修内容は、司法制度の歴史や、司法書士の主な業務、司法書士としてのマインド・職責・倫理などです。
※参考として、令和6年度のスケジュールを掲載します。令和7年度の情報が分かり次第更新します。
| 視聴グループ | ブロック | 受講期間 |
|---|---|---|
| 第1グループ | 北海道・東北・中部・近畿・ 中国・四国・九州 | 令和6年12月10日(火)0時00分~ 12月27日(金)23時59分 |
| 第2グループ | 関東 | 令和7年1月6日(月)0時00分~ 1月23日(木)23時59分 |
 LEGAL JOB BOARD 北澤
LEGAL JOB BOARD 北澤
▶︎ 司法書士の求人を見る
ブロック新人研修の日程・内容
ブロック新人研修は実務を意識した研修で、全国8ブロックごとで1~3週間程度行われます。ほとんどのブロックにおいて、集合形式(対面)で行われます。
受講するブロックですが、開業または勤務予定地のブロックでの受講が推奨されています。
※参考として、令和6年度のスケジュールを掲載します。令和7年度の情報が分かり次第更新します。
| ブロック | 定員 | 日程 | 実施形式 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 35名 | 令和7年1月27日(月)~2月2日(日) | 集合 |
| 東北 | 50名 | 令和7年1月12日(日)~1月20日(月) ※1月16日(木)は休講日 | 集合 |
| 関東 | 330名 | Web:令和6年12月16日(月)~令和7年1月19日(日) 集合:令和7年1月18日(土)~1月19日(日) | 集合・Web |
| 中部 | 75名 | 令和7年1月13日(月・祝)~1月19日(日) | 集合 |
| 近畿 | 140名 | 令和6年12月14日(土)~16日(月)、20日(金)~22日(日) 令和7年1月4日(土)~5日(日)、1月11日(土)~13日(月・祝)、17日(金)~18日(土) | 集合 |
| 中国 | 40名 | 令和7年1月9日(木)~1月15日(水) | 集合 |
| 四国 | 25名 | 令和7年1月10日(金)~1月16日(木) | 集合 |
| 九州 | 75名 | 令和7年1月11日(土)~1月18日(土) | 集合 |
実施場所などの詳細は、「令和6年度 司法書士新人研修のご案内」でご確認いただけます。
各司法書士会 新人研修について
各司法書士会が主催する新人研修は「集合研修」と「配属研修」に分かれて実施されます(※司法書士会によってはどちらか一方のみの場合もあり)。
費用や申込方法は受講する司法書士会によって異なります。受講する司法書士会のホームページをご確認ください。
集合研修
「集合研修」は座学で司法書士実務を学ぶ研修です。
司法書士会によって内容も異なりますが、司法書士倫理、不動産登記、商業登記、相続登記、裁判書類作成等の業務について、先輩司法書士が実務経験を交えて話してくれます。
なかでも、東京司法書士会の新人研修は、テキストが実務においても使えると言われており特に好評です。そのため、他県の方も多く参加します。
配属研修
「配属研修」は司法書士事務所へ配属され、1~3ヶ月ほど実務を学ぶ研修です。
申し込む際には、登録予定の司法書士会を選ぶことが推奨されています。研修先の事務所は希望を出せますが、希望者が多い場合は抽選が行われることもあるようです。
司法書士会新人研修の詳細は、司法書士会によって異なります。不明点などは、各司法書士会に問い合わせるのが良いでしょう。
 LEGAL JOB BOARD 北澤
LEGAL JOB BOARD 北澤
▶︎ 司法書士の求人を見る
新人研修は働きながら受けられる?
司法書士の新人研修は、働きながら受けることができます。
実際に、司法書士事務所で勤務しながら、仕事と研修を両立している方は例年多くいらっしゃいます。事務所は研修への理解があるため、出勤日と研修が被ったら休みを取得することも可能です。
一般企業など司法書士業界以外で勤務している場合も、事情を説明して有休などを消化し、研修に参加する方が多いようです。また、早めに引き継ぎなどの準備をしておくことも大切です。
新人研修を受けないとどうなる?
合格後1年以内に司法書士として働く予定の方は、新人研修を受けましょう。新人研修は、合格後1年以内に司法書士として登録・司法書士会への入会をする方を対象としています。
すぐに司法書士として働く予定がない場合、受けない・翌年以降に受けるといった選択も可能です。しかし司法書士として働く(登録する)のであれば、新人研修の受講は避けられません。
司法書士登録をしたいが、やむを得ない事情で新人研修を受けるのが難しいといった方は、事前に各司法書士会に問い合わせることをおすすめします。
司法書士 新人研修の申込方法・費用
新人研修の申込方法と受講にかかる費用を解説します。
※以下は令和6年度の内容です。令和7年度の情報が分かり次第、更新いたします。
中央新人研修・ブロック新人研修
日司連研修総合ポータルに、令和6年11月5日(火)に新人研修申込専用サイトが掲載される予定です。申込受付期間は、令和6年11月5日(火)0:00〜11月18日(月)23:59です。
提出書類は以下のとおりで、11月25日(月)までに申込専用サイトにアップロードします。
- 司法書士となる資格を有する書面の写し(合格証書・認定証書等)
- 住民票(受講申込日より3ヵ月以内・現住所と一致するもの)
中央新人研修とブロック新人研修の受講料は、合わせて7万7,000円(税込)。
内訳として、中央新人研修が4万4,000円、ブロック新人研修が3万3,000円です。受講ブロックによっては、別途費用がかかるケースもあるとのこと。
受講料の支払いは、申込画面の案内に従って、11月20日(水)までに行う必要があります。
各司法書士会による新人研修
司法書士会ごとの新人研修は、受講する司法書士会によって申込方法・費用ともに異なります。申込方法・受講料ともに、受講予定の司法書士会のホームページなどで情報をお確かめください。
参考までに、令和6年度 東京司法書士会主催の新人研修の受講料は3万3,000円(税込)となっています。
司法書士の登録について
司法書士として働くには、必ず司法書士登録を行わなくてはなりません。これは、司法書士法第8条の規定によって定められています。
司法書士登録までの主なステップは以下の通りです。
- 司法書士試験に合格
- 新人研修を受講
- 日本司法書士連合会に登録申請(各司法書士会を経由して登録申請書を提出)
登録の要件や費用、必要書類などの詳細は、以下の記事をご覧ください。
あわせて読みたい記事
特別研修・認定考査について
新人研修ではありませんが、認定司法書士になるための「特別研修」も例年多くの方が受講します。特別研修を受講しないと認定考査試験が受けられません。
認定考査試験に合格すると、140万円以下の民事訴訟案件に対応できる認定司法書士として活躍の場を広げられます。
必須の研修ではありませんが、全司法書士のうち約8割が認定司法書士であり、多くの方が受講していることが分かります。詳細は以下の記事をご覧ください。
あわせて読みたい記事
司法書士の求人・キャリア情報をチェックする
司法書士業界に特化した転職サイト「リーガルジョブボード」には、司法書士の求人が豊富に掲載されています。
未経験の方、合格者の方向けの求人も取り揃えていますので、ぜひ一度ご覧ください。
▶︎ 司法書士の求人を見る
希望に沿った求人、自分が応募できる求人のみを効率よく知りたい方は、キャリアアドバイザーが求人を選定いたします。
 LEGAL JOB BOARD 北澤
LEGAL JOB BOARD 北澤
あわせて読みたい記事
▼リーガルジョブマガジンとは
司法書士の転職・キャリアに関するお役立ち情報や、業界知識・動向、インタビュー記事などを発信するメディアです。
記事一覧を見る