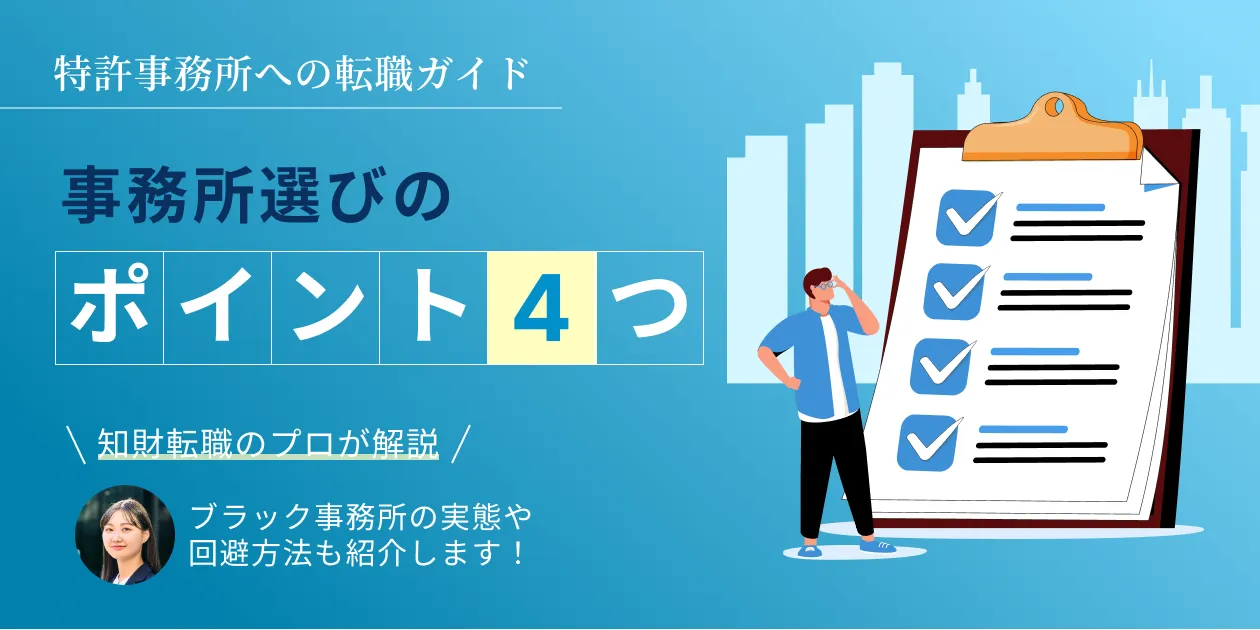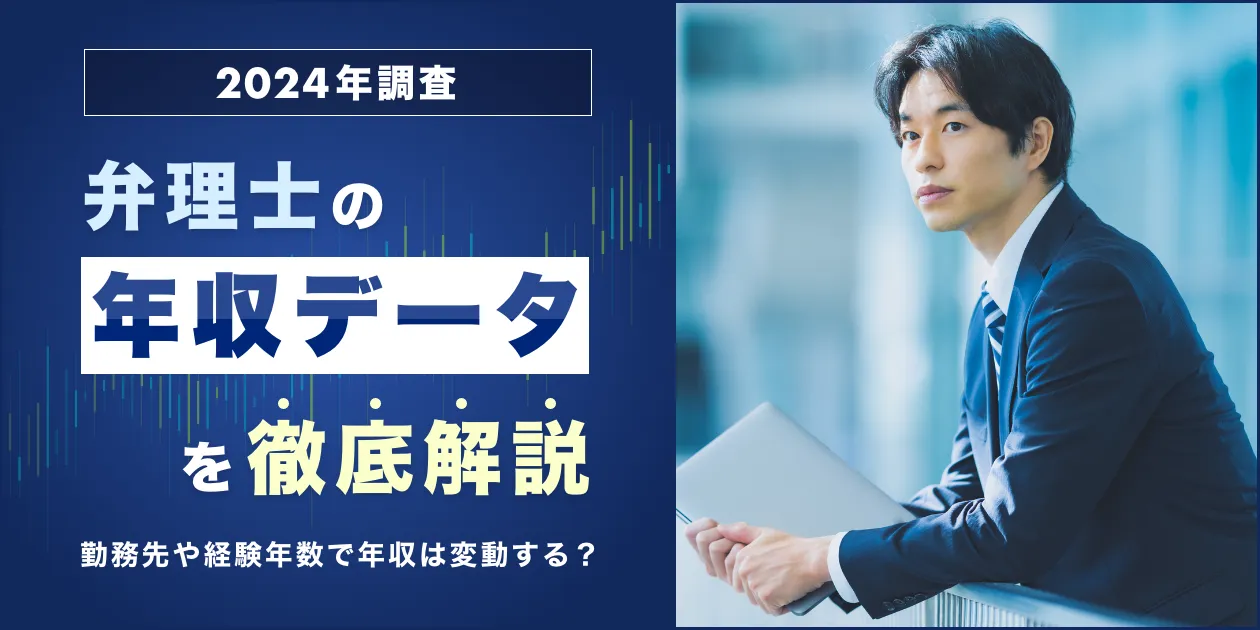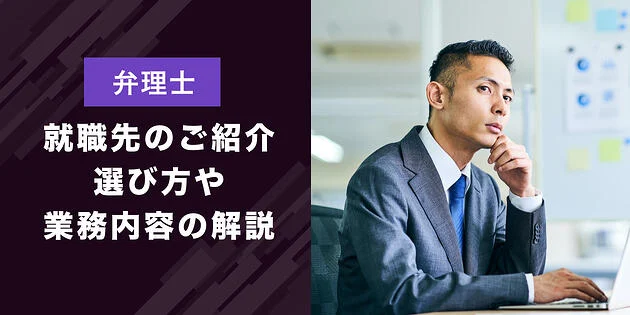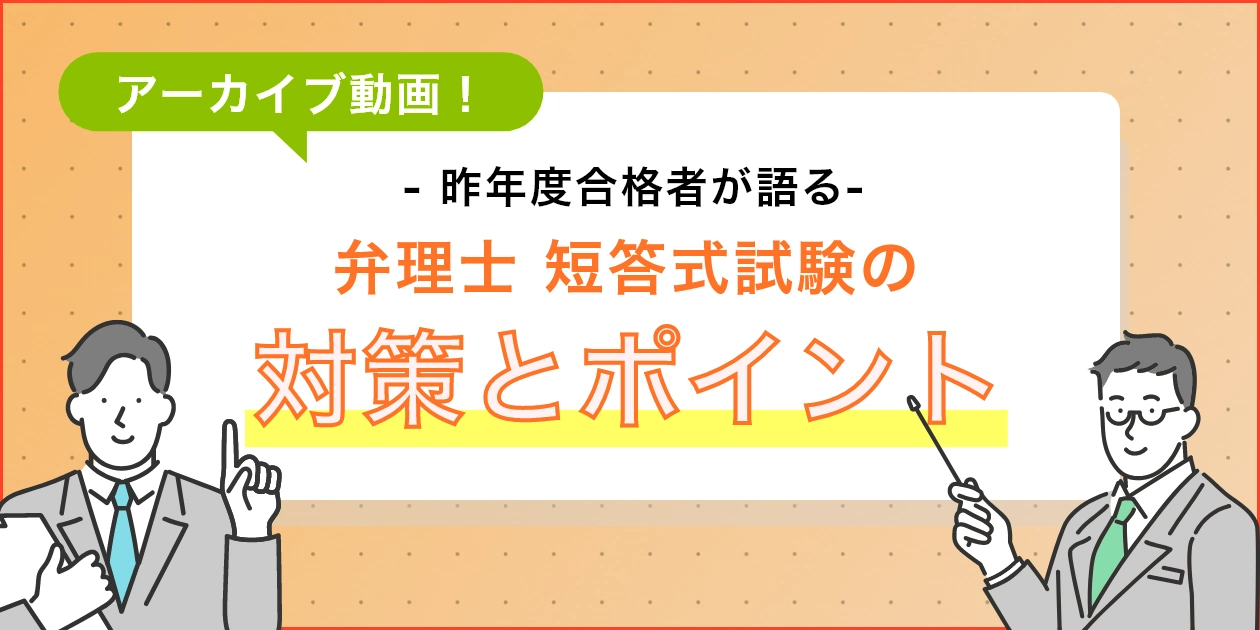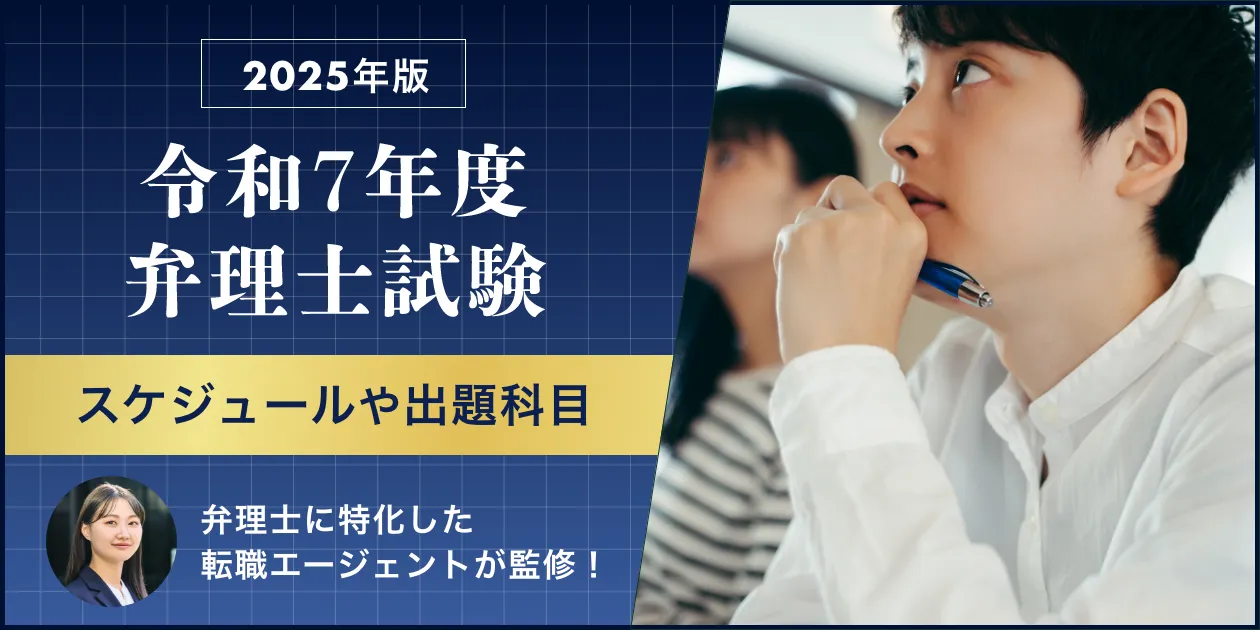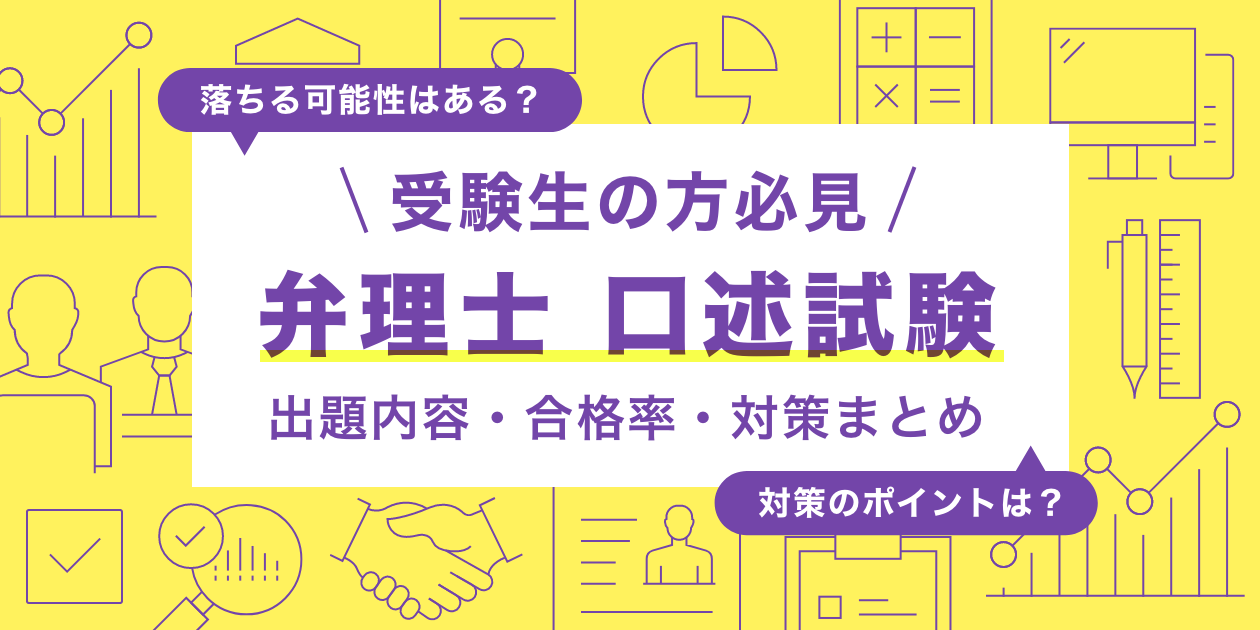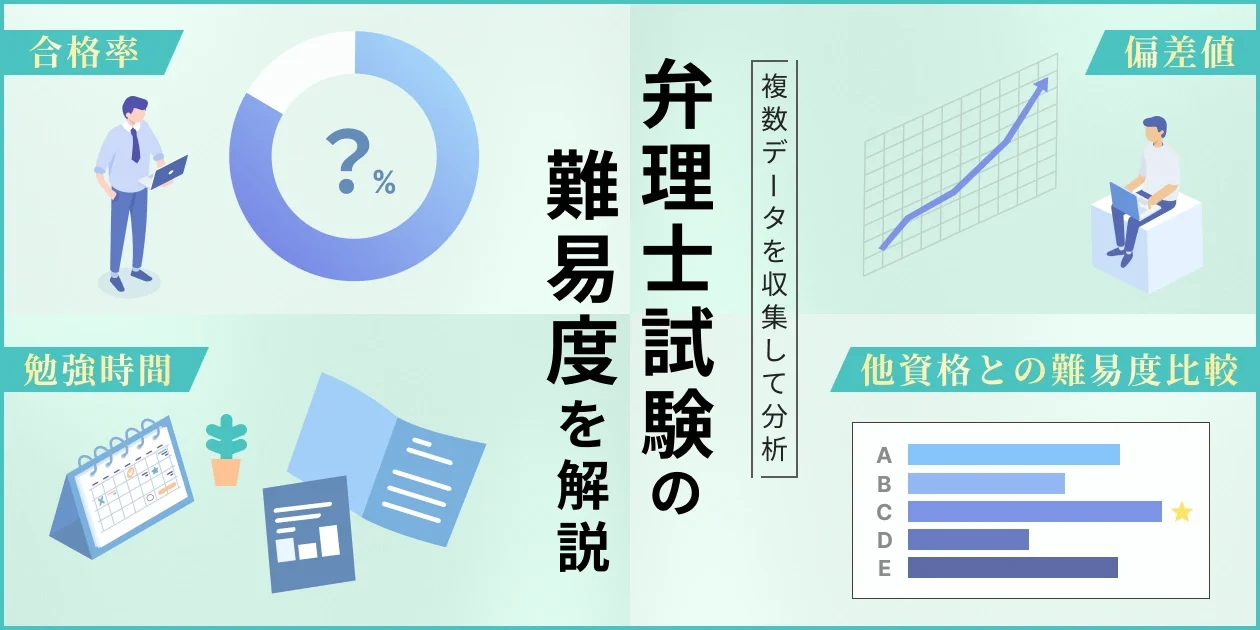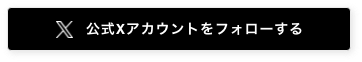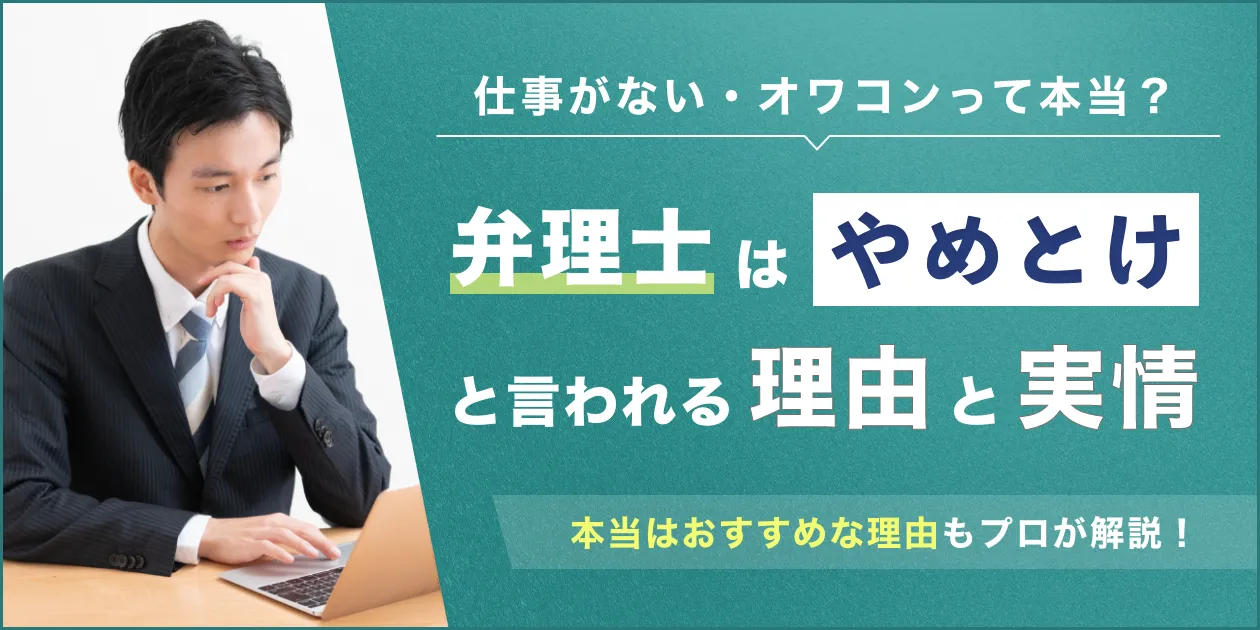
弁理士はやめとけ・仕事がない・オワコンといわれる理由と実情を解説

by LEGAL JOB BOARD 正田
キャリアアドバイザー
- 担当職種:
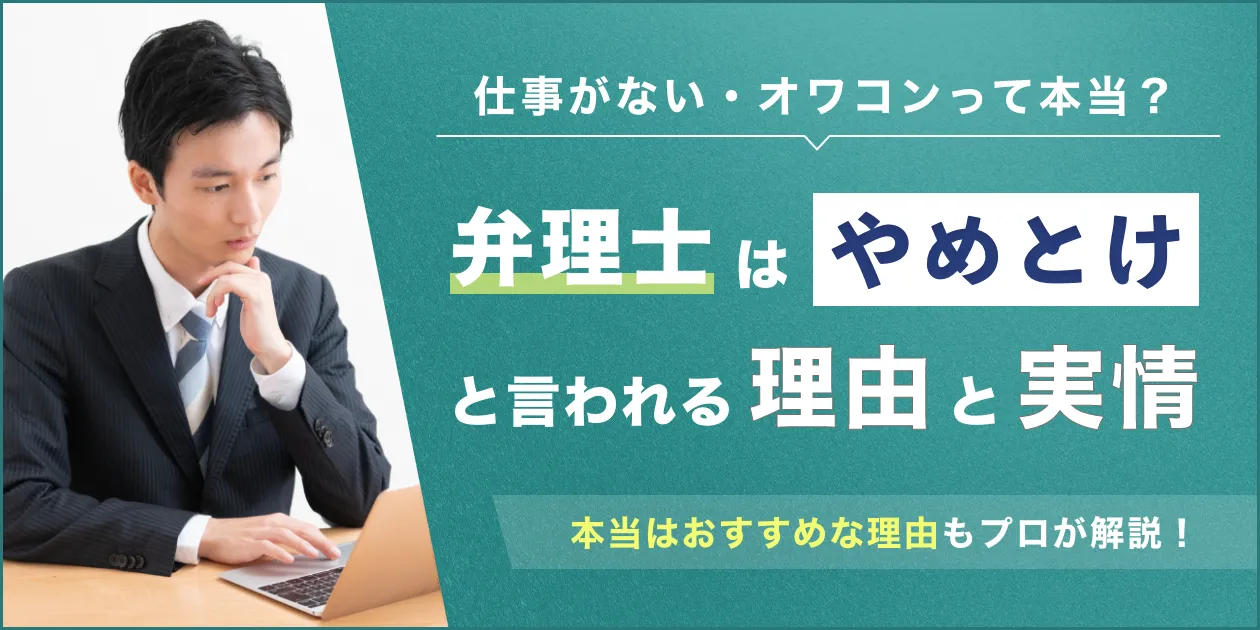
弁理士・知財に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の正田です。
本記事では、「弁理士はやめとけと言われる理由」や「本当は弁理士がおすすめな理由」をご紹介します。
▼この記事で分かること
・なぜ「弁理士はやめとけ」と言われるのか
・特許出願数から見る弁理士の今後の需要
・弁理士として働くメリット
・食いっぱぐれない弁理士になるポイント
▼この記事を読んでいただきたい方
・弁理士を目指すか否か悩んでいる
・弁理士として勤務しており現在の勤務先に何らかの不安を感じている
・知財業界の将来性に不安を感じている
弁理士はやめとけといわれる理由
弁理士は知的財産に関する専門家で、特許などの出願手続きを代理で行うのが主な仕事です。インターネットの普及によりグローバル化が進む昨今において、知的財産への注目は集まっています。
このように社会的貢献性の高い弁理士ですが、なぜ「やめとけ」「仕事がない」「オワコン」などと言われるのでしょうか。
本ブロックではその3つの理由について解説していきます。
- 弁理士として独り立ちするのに約5~6年必要とされている
- 案件獲得の競争が激化しつつある
- ブラックな勤務先が存在する
弁理士として独り立ちするのに約5~6年必要とされているため
個人差はありますが、弁理士資格の取得には平均2〜4年をかける方が多い印象です。
また弁理士実務を習得するには、それなりの時間を要します。特に明細書作成を完全に一人で行えるようになるには、最低でも2〜3年かかるのが一般的とされています。
受験勉強や実務習得に時間がかかり、時間帯効果が悪いと感じる場合もあります。そのため、「弁理士はやめとけ」という声が上がるようです。
関連記事:弁理士資格は働きながら取得可能である理由・合格体験記
案件獲得の競争が激化しつつあるため
弁理士数は年々増えている一方で、弁理士のメイン業務である国内特許出願の件数は減少傾向にあります。そのため、案件獲得の競争が激化しつつあると言えるでしょう。
日本弁理士会に登録している弁理士数は増加を続け2024年5月末時点で1万2,281人。一方で国内の特許出願件数は減少傾向にあり、2019年以降は年間30万件を下回っています。
しかし、WIPO(世界知的所有権機関)の発表によるとPCT(Patent Cooperation Treaty)国際出願件数は例年高い水準を維持しています。
海外でも知財の重要性が再認識される機会が増えており、世界的に見ると弁理士の需要は高まっていると言えます。
ブラックな勤務先も存在するため
働きやすい特許事務所が増加傾向にある一方で、以下のようなブラック特許事務所もいまだに存在しています。
- 上司からパワハラなどを受ける
- 薄利多売でなかなか給与が上がらない…
- 十分な指導がないのに、仕事ができないと叱責される
ただ、当然このような事務所ばかりではありません。ブラックな事務所を回避するには、職場選びの段階で情報収集を徹底するのがベストです。
あわせて読みたい記事はこちら
弁理士はやめとけと言われても目指す人が多い理由
先のブロックでは「弁理士はやめとけ」と言われる理由を解説しましたが、弁理士は魅力・やりがいも多くある仕事です。弁理士資格を目指す人が多い主な理由3点について解説していきます。
- 世界的に弁理士の需要が高まっている
- 一般的な会社員よりも高収入が目指せる
- 在宅勤務やテレワークが可能
世界的に弁理士の需要が高まっているため
2022年まで国内の特許出願数は減少傾向にありましたが、2023年には前年比3.6%と増加傾向に転じ始めています。
.webp)
また国際出願件数も増加傾向にあり、2023年には355万件を超えて過去最高件数となっています。
国別に見ていくと、最も出願件数が多いのは中国で、次いでアメリカ、日本の順です。
-1.webp)
アップルとサムスンの特許訴訟など、知財の重要性が再認識される機会も増えています。世界では損害賠償額を引き上げる動きもあり、知財の専門家である弁理士は必要不可欠な存在です。今後も需要のある職種であり、「弁理士は仕事がない」とは言えないでしょう。
外国関連の仕事を積極的に行いたい場合など、英語力があると弁理士としての価値がより高まります。訴訟関連では、付記弁理士になる方もいらっしゃいます。
一般的な会社員よりも高収入が目指せるため
弁理士の平均年収は700万円〜750万円ほどで、日本の給与所得者の年間平均給与458万円を上回っています。
弁理士の年収は、経験や勤務先などの条件で変動しますが、給与水準は高い傾向にあります。また出来高が給与に反映される評価制度であれば、実力次第で高収入を目指すことも可能です。実際に、年収1,000万円を超える弁理士も存在します。
働いた分・成果を上げた分だけ高収入を得たい方などは、やりがいを感じながら働けるでしょう。
あわせて読みたい記事はこちら
在宅勤務やテレワークが可能なため
事務所によって可否は異なりますが、在宅勤務やテレワークを取り入れて働く弁理士は多くいます。弊社が2023年に実施した調査では、41事務所中39事務所で弁理士の在宅勤務・テレワークが実施されていました。

在宅勤務やテレワークを活用し、家事や育児などと仕事を両立している方もいます。融通が利く事務所では、企業よりも自由な働き方をされている弁理士の方が多い印象です。
経験値や調整力は必要ですが、弁理士は比較的自分で仕事量や時間をコントロールしやすい傾向にあります。そのため、ワークライフバランスを大切にして働くことも可能です。
【弁理士】在宅勤務OKな求人一覧
弁理士に向いている人の特徴
では、どのような人が弁理士に向いているのでしょうか?以下の特徴に一つでも当てはまる場合、弁理士の適性がある可能性が高いです。
理論的な説明ができる
明細書作成や拒絶理由通知への対応には、事実に基づいた理論的な説明能力が必要です。本来ならば権利化できる技術やアイデアも、説明次第では審査を通過できない可能性があります。そのため、理論的な思考力・説明力は弁理士に不可欠な要素です。
新しい物事に興味を持てる
弁理士は常に新しいアイデアや発明に関わることができる仕事です。知的好奇心が旺盛で、新しい物事に興味を持てる方は弁理士に向います。また、外国出願を行う事務所も多いため、海外の動向にも興味を持てると尚良いでしょう。
情報収集能力に優れている
弁理士のメイン業務である特許出願書類・明細書の作成は、情報を収集してまとめる能力が試されます。技術的な知識・情報だけでなく、関連法の改正など、自身の技術分野に関する最新情報を常に仕入れておくのが望ましいです。
「弁理士・知財業界に転職するか迷っている」「応募可能な求人があるか知りたい」といった方は、リーガルジョブボードの知財専門キャリアアドバイザーまでお気軽にお問い合わせください。
食いっぱぐれない弁理士になるために
弁理士として食いっぱぐれない、安定して働くことや高収入を実現するため、押さえておきたいポイントを解説します。
付加価値で周囲と差別化を図る
例えば、クライアントは出願の対応だけでなく、知財戦略や出願方針などを提案してくれる弁理士を頼りたくなるものです。ヒアリング時など積極的に提案する姿勢を見せるのも良いでしょう。
また、弁理士以外の資格を取得し、ダブルライセンスで活躍する方もいます。例として中小企業診断士の資格があれば、経営面の相談もできる弁理士として中小企業から重宝されるケースがよくあります。
関連記事:弁理士と相性が良いダブルライセンス一覧|資格取得のメリットは?
AIなどの最新技術を活用する
今後、AIをうまく活用することは必須の時代になってきます。すでに商標分野でAIを利用している部分もあり、弁理士の負担軽減のための活用が期待されます。
最新技術を活用することで業務効率化を実現でき、より多くの案件を受けたり、専門性の高い高度な案件・業務に携われるはずです。
幅広い技術分野に対応できるようになる
弁理士にはそれぞれ、得意な技術分野が存在するかと思います。しかし、その分野しか対応できないと、どうしても案件数に限界があります。
今後成長するであろうAIや情報分野を習得したり、電気分野が得意であれば電子や制御、電装、半導体と徐々に分野を広げたり、担当できる案件を広げるのも良いでしょう。
指導力を身につける
弁理士の業務指導は難しいとされており、新人教育ができる方は市場価値が高いです。実際、採用側から「指導経験がある弁理士はいませんか?」と相談があることも。
新人や後輩を育成することは、業務効率化や事務所の成長にも繋がります。興味がある方や、将来マネジメントに携わりたい方は、積極的にチャレンジされてはいかがでしょうか。
まとめ
本記事では「弁理士はやめとけ」と言われる理由と業界全体の動向について解説しました。
「弁理士はやめとけ」と言われるのはこの3つの理由が挙げられます。
- 独り立ちするまでに相当の時間を要し、タイムパフォーマンスが良くない
- 国内の特許出願件数が減少傾向にあり、業界全体が停滞している印象がある
- 労働環境が良くない勤務先がある
ですが、PCT国際出願件数が高い水準を維持していることからも弁理士は世界的にも需要があり、社会貢献度が高い専門職と言えます。
また在宅勤務・テレワークが導入されやすい業界のため、ワークライフバランスを重視して働くこともできます。
一筋縄ではいかない資格ですが、ぜひ候補の1つに入れてみてください。
この記事を最後まで読んでくださった皆さまへ
弁理士・知財業界への就職・転職に関連し、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?
- 働きながらの弁理士受験について詳しく知りたい
- 自分の経歴で特許技術者になれるのか知りたい
- 転職に最適なタイミングを相談したい
といった方は、弁理士・知財に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」にご相談ください。情報収集や相談のみでもご利用可能で、転職を無理強いすることは決してございません。安心してお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい記事はこちら