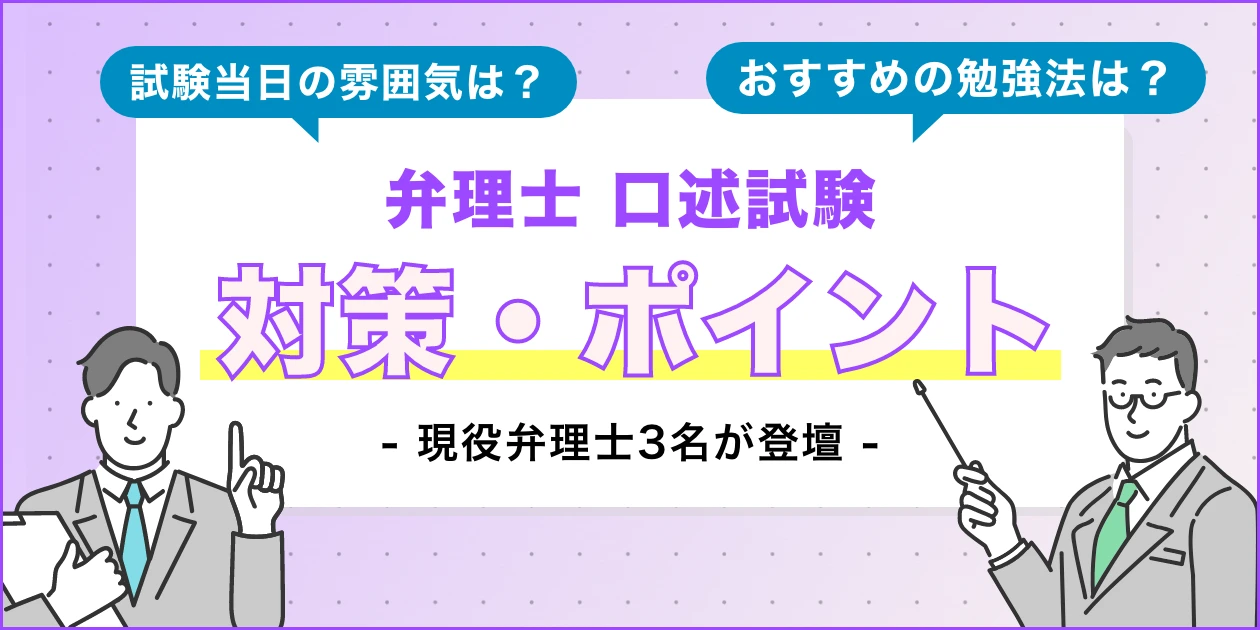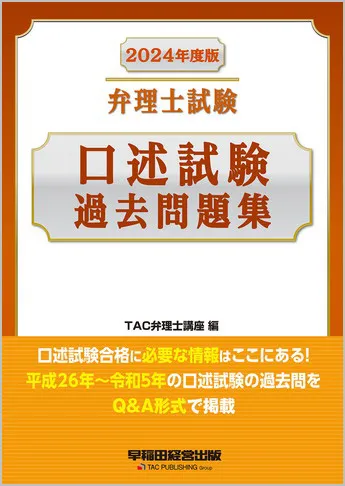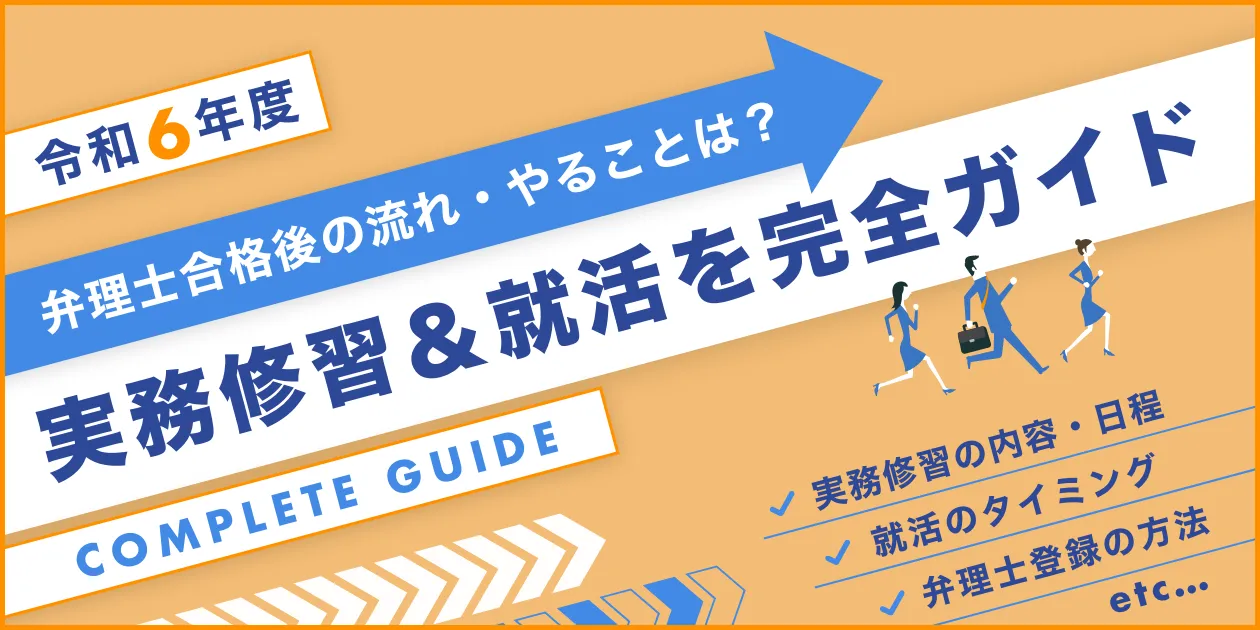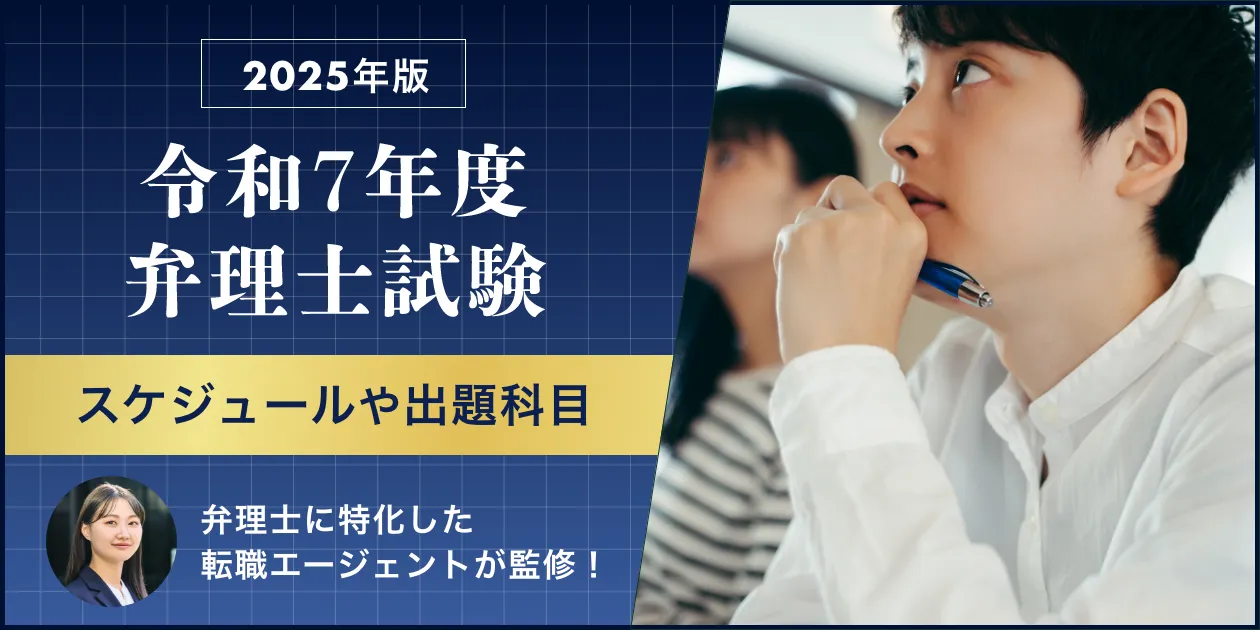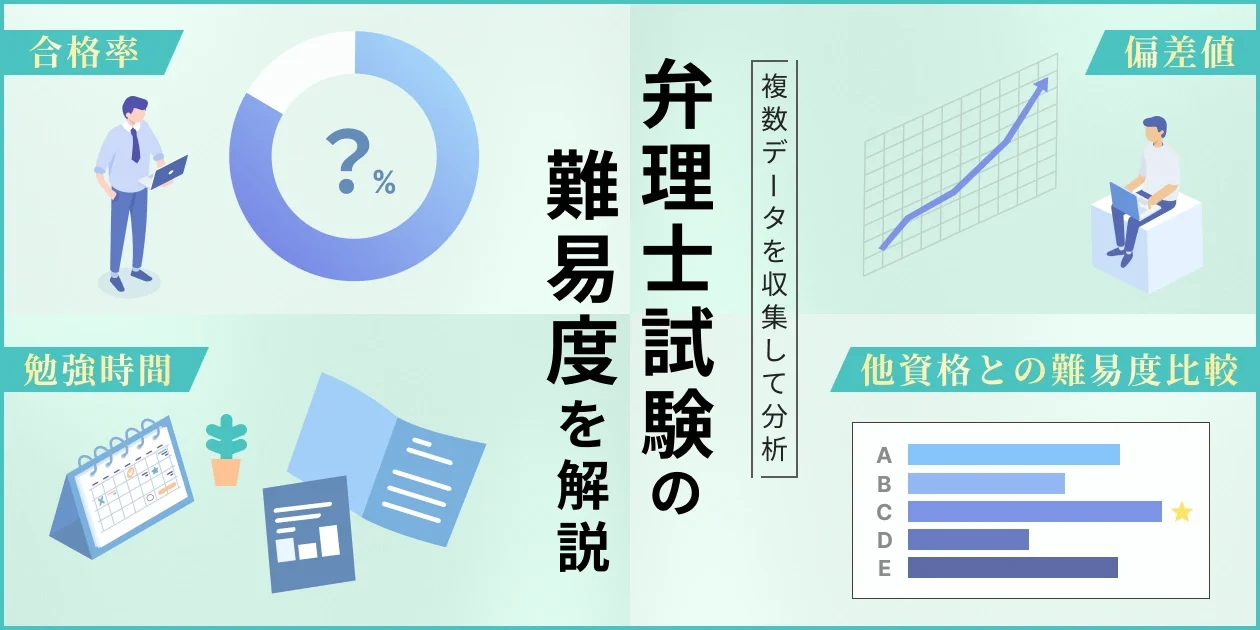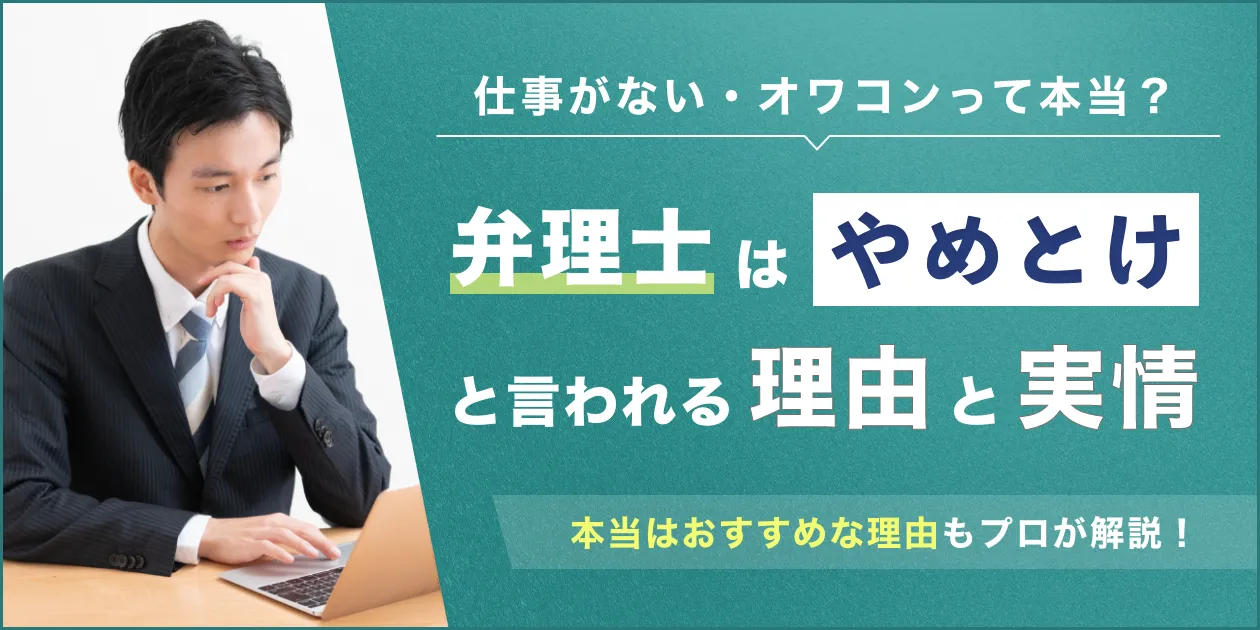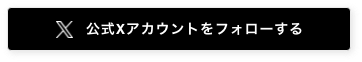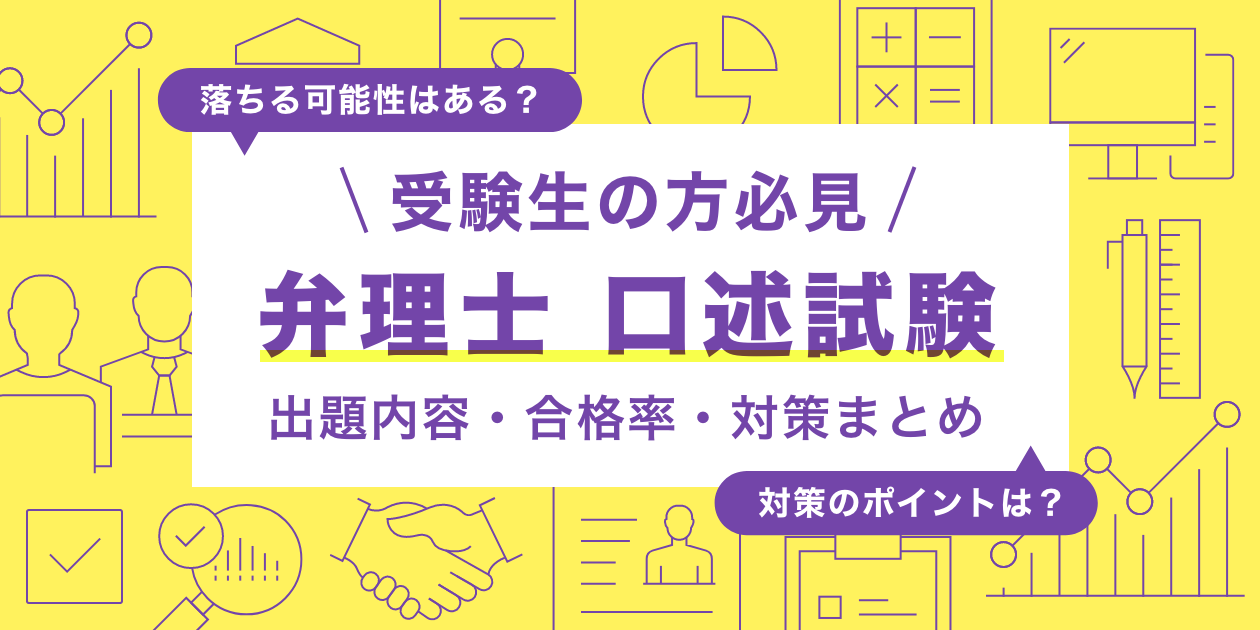
【2024年】弁理士 口述試験の日程・対策方法|落ちる可能性はある?

by LEGAL JOB BOARD 三島善太
キャリアアドバイザー
- 担当職種:
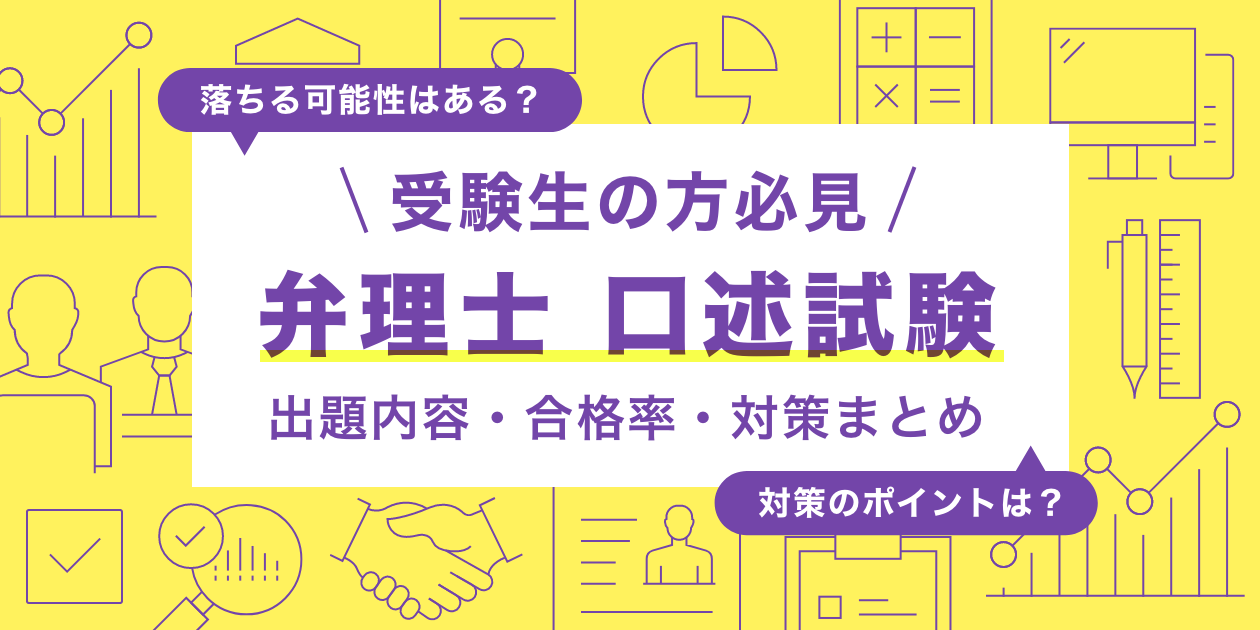
弁理士・知財に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の三島です。
本記事では、「弁理士 口述試験の出題内容や合格率、対策方法」などを解説します。ぜひご覧ください。
【令和7年度弁理士試験受験者必見】
8/28(木)19:30よりオンラインにて、弁理士口述試験“相談会”を開催します。
昨年合格者が試験会場のリアルな雰囲気や、実際に行った試験対策を語ります。
▶詳細はこちら
昨年の合格者が語る、口述試験に向けた対策はこちら
この記事の目次
2024年(令和6年度) 弁理士 口述試験の概要
口述試験は弁理士試験の最終試験で、試験官が出す問題に口頭で答える面接形式で行われます。
| 日程 | 2024年10月19日(土)~21日(月)のいずれかの日 ※受験地は東京のみ |
| 試験科目 | 工業所有権(特許・実用新案、意匠、商標)に関する法令 |
| 試問方法 | ・受験者1名ごとに試問する ・受験者は各科目の試験室を順次移動する |
| 試験時間 | 3科目(特許・実用新案、意匠、商標)それぞれ10分程度 |
| 合格基準 | A・B・Cのゾーン方式で採点し、合格基準はC評価が2科目以上ないこと |
| 免除条件 | 特許庁において審判または審査の事務に5年以上従事した方 |
口述試験では法文の参照が可能です。必要な場合は、試験委員の許可を受けてから、用意されている弁理士試験用法文を確認できます。
「合格後の転職・就職に備えて、早めに動きたい」「転職のタイミング・事務所選びを相談したい」といった方は、リーガルジョブボードの弁理士専門キャリアアドバイザーまで、お気軽にご相談ください。
弁理士口述試験の合格率
口述試験の合格率は、例年90~99%程度です。直近3年の口述試験の合格率は90%台で、令和5年度は約94%でした。
.webp)
口述試験は合格率が高く感じられますが、短答式・論文式試験を突破した方が受験するため、納得の結果ではないでしょうか。
過去の口述試験問題テーマ
口述試験の問題テーマは、毎年公開されています。質問の仕方こそ違えど、重要な概念は繰返し出題される傾向にあります。
令和5年度 口述試験テーマ
| 10月21日 | 10月22日 | |
|---|---|---|
| 特許・実用新案 | 明細書等の補正 | 訂正審判と訂正の請求 |
| 意匠 | 意匠に係る物品、意匠権の効力、意匠の登録要件 | 意匠の公示、他の権利との関係 |
| 商標 | 商標の保護 | 不使用取消審判 |
令和4年度 口述試験テーマ
| 10月22日 | 10月23日 | |
|---|---|---|
| 特許・実用新案 | 特許無効審判の請求等の取下げ | 明細書等の記載要件と特許発明の技術的範囲 |
| 意匠 | 意匠登録を受けることができない意匠 | 職務創作・関連意匠 |
| 商標 | 商標権の効力・侵害 | 登録要件 |
「合格後の転職・就職に備えて、早めに動きたい」「転職のタイミング・事務所選びを相談したい」といった方は、リーガルジョブボードの弁理士専門キャリアアドバイザーまで、お気軽にご相談ください。
口述試験の対策方法
口述試験の対策は、練習会や講習会、模擬練習などを活用する方が多いです。それぞれ紹介します。
会派の練習会に参加する
様々な会派が口述試験の「練習会」を開催しており、大体は論文試験の合格発表後に申し込みがスタートします。
厳しく派閥があるわけではありませんが、出身大学OBの多い会派や、知り合いの弁理士と同じ会派に行く方が多い印象です。会派の練習会への参加は、業界内で顔を売ることにも繋がるでしょう。
予備校の講習会を活用する
各予備校でも例年、口述試験の講習会などが行われています。
費用がかかりますが、予備校によっては想定問題集をもらえるなどの特典があるようです。
受験仲間や先輩と模擬練習
受験仲間がいる方は、お互いに出題し合って練習する方法もあります。これは弁理士の方が教えてくださいました。
職場や身近に、先輩弁理士がいる方は練習相手になってもらうのも良いでしょう。
口述試験の対策や当日のエピソードなど、令和5年度の合格者にリアルなお話をしていただきました。以下の記事をぜひご覧ください。
口述試験対策におすすめの本
口述試験の対策におすすめなのが、『2024年度版 弁理士試験 口述試験過去問題集』です。
過去10年分の口述試験の様子をQ&A形式で再現しており、即興でどう答えたらよいのかを端的に解説しています。
「合格後の転職・就職に備えて、早めに動きたい」「転職のタイミング・事務所選びを相談したい」といった方は、リーガルジョブボードの弁理士専門キャリアアドバイザーまで、お気軽にご相談ください。
口述試験に落ちる可能性はある?
口述試験の合格率は、例年90%台と高くなっています。ただ合格率が100%でない以上、不合格の方もいるのが事実です。
実際に、口述試験に不合格となってしまった方から直接お話を伺ったことが何度かあります。その方々がおっしゃっていた原因は、「対策不足」や「緊張」が多かったです。
現役弁理士のとある先生は、「口述試験は短答式で問われるような知識も必要な傾向にある」「実際に私も頭が真っ白になった」といった旨のお話をされていました。
また、面接形式の口述試験は、知識だけでなくコミュニケーション能力や態度も重要です。口述試験に落ちる可能性はそこまで高くありませんが、十分に対策することが望ましいでしょう。
口述試験に合格した後の動き・やること
2024年(令和6年度)弁理士試験の最終合格発表は、11月11日(月)の予定です。
弁理士試験に合格した後は、実務修習を修了しないと弁理士登録ができません。
また、弁理士として働く方は、転職・就職活動も本格化します。就職・転職活動は余裕を持って進めることが成功のカギとなります。
ここ最近の受験生の動向としては、
- 論文式試験の必須科目・選択科目の受験後~結果発表
- 論文式試験の合格発表後
から、転職活動を行う方が多いです。このタイミングで、採用側(主に特許事務所)も、合格見込み者を対象とした採用活動を活発化させる傾向にあります。
就活のポイントや実務修習スケジュールは、以下の記事でご確認ください。