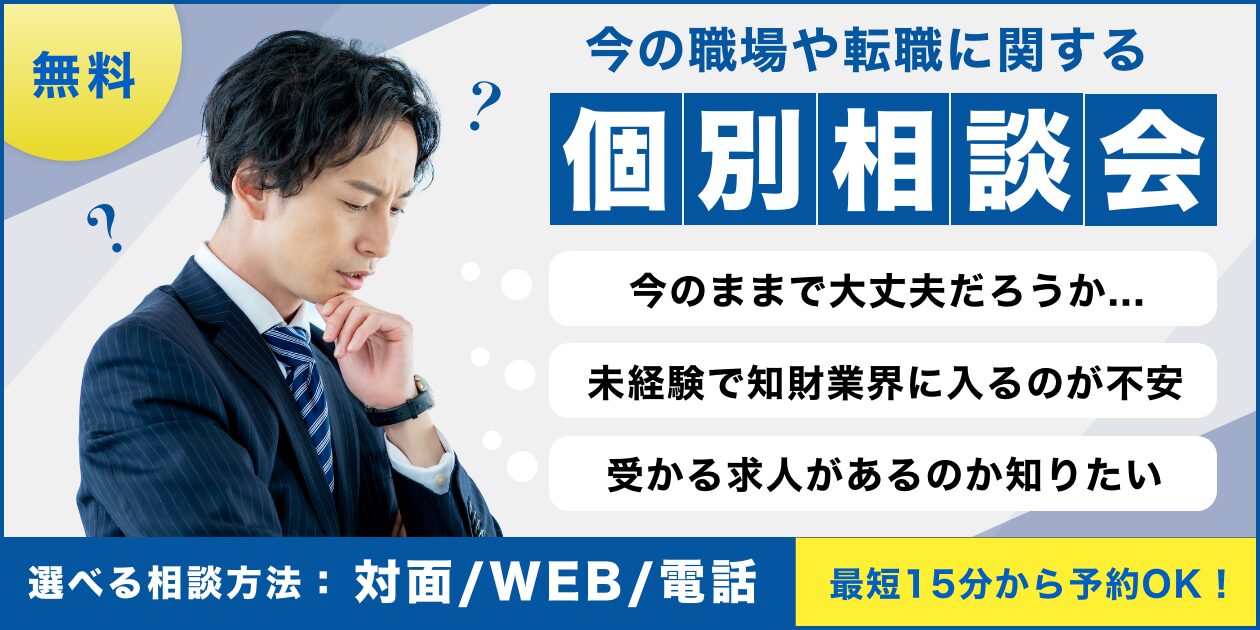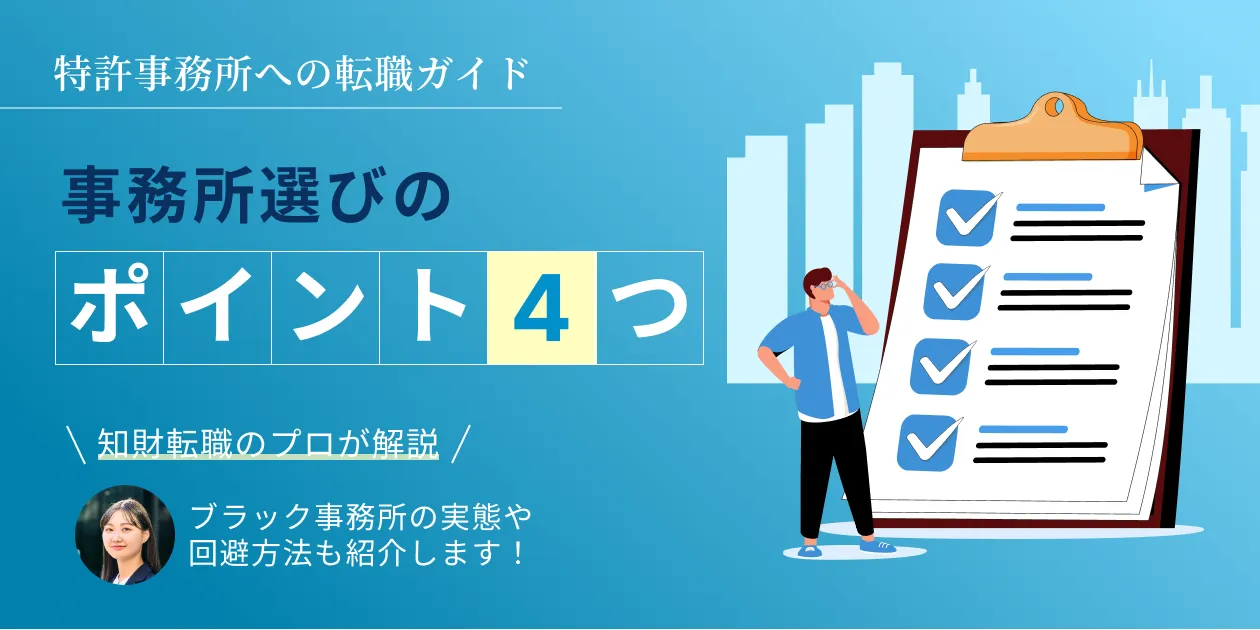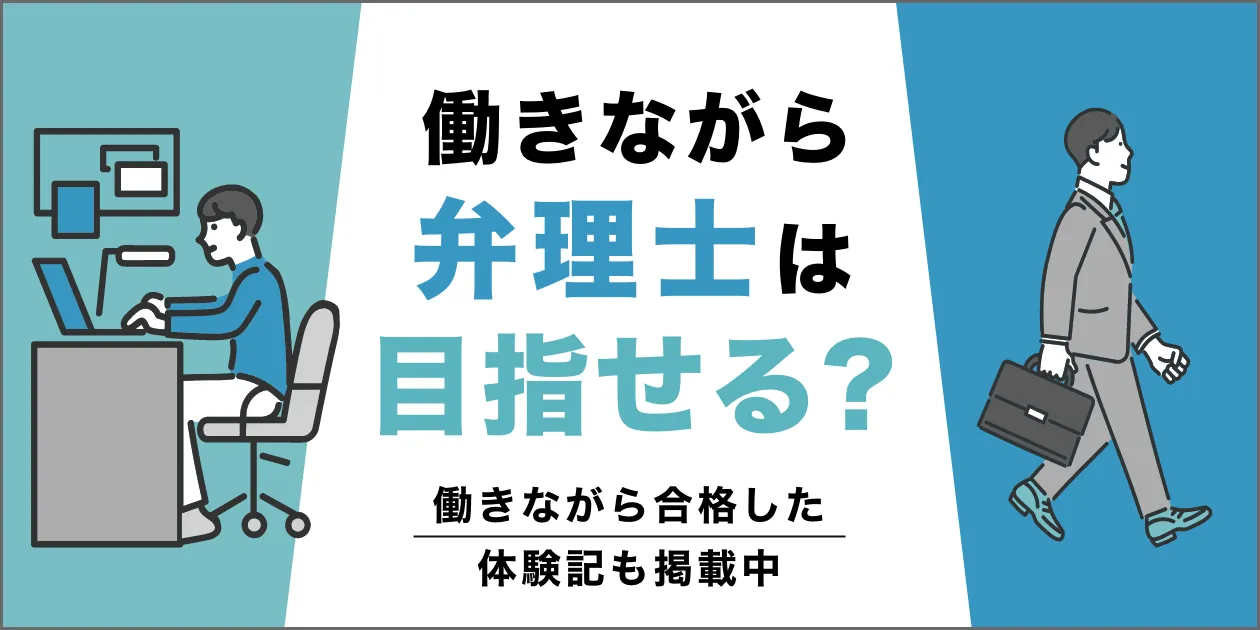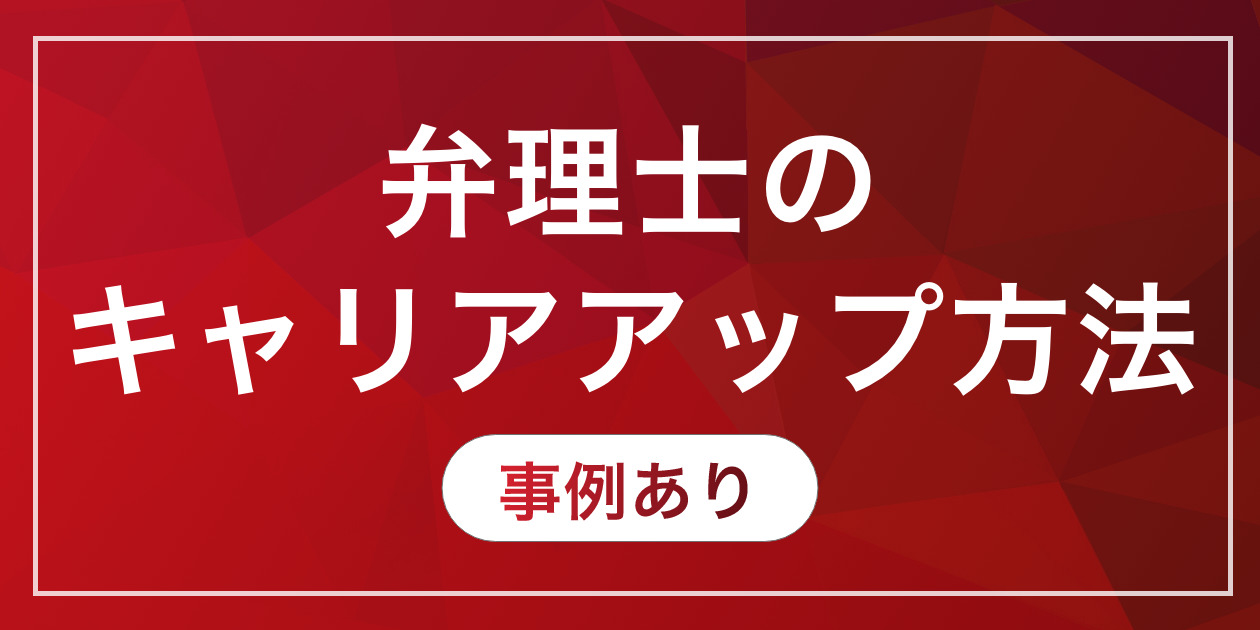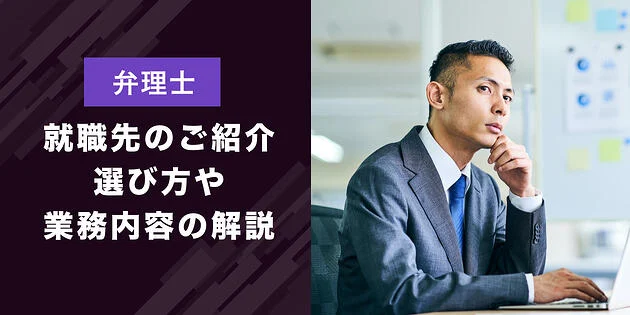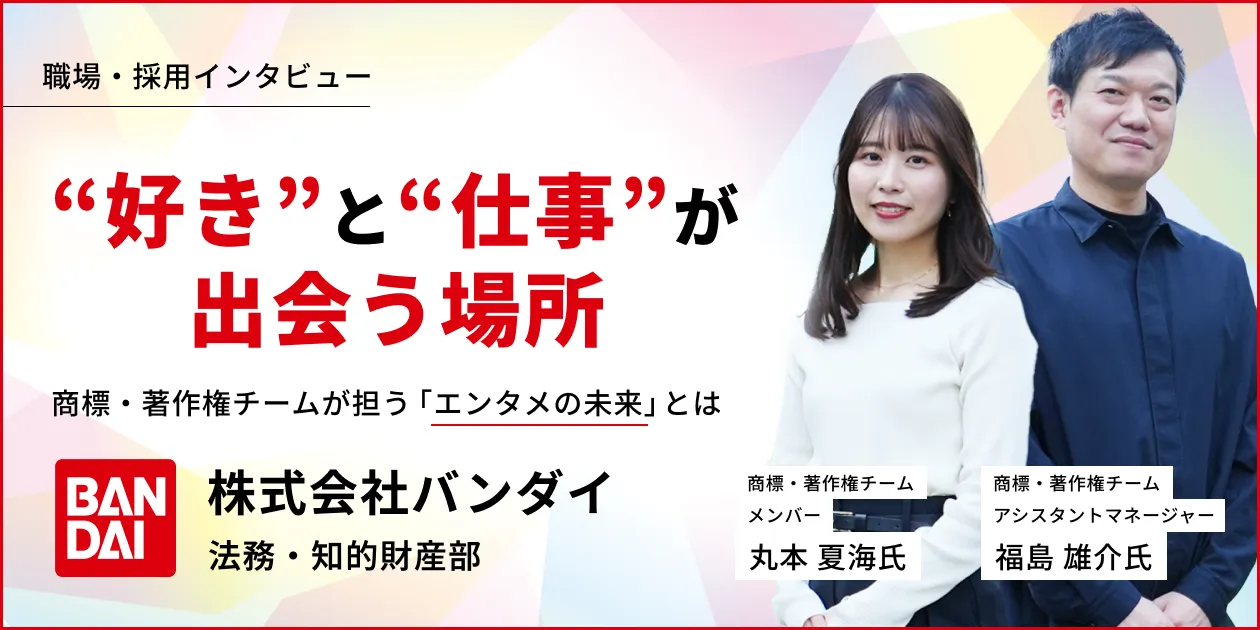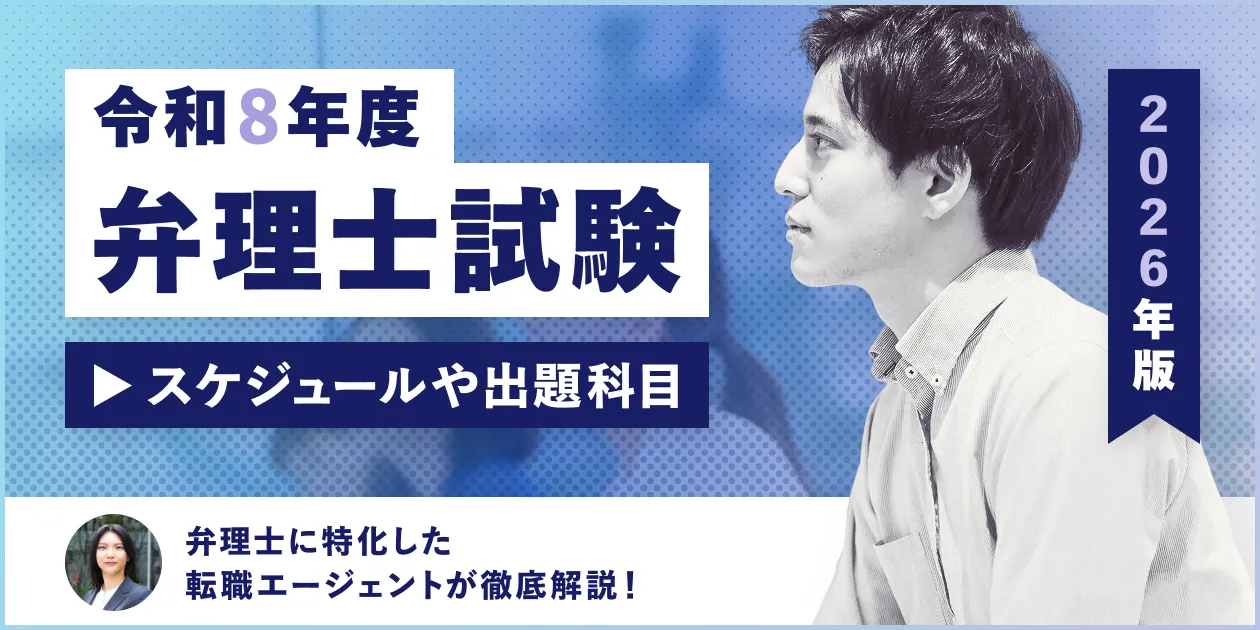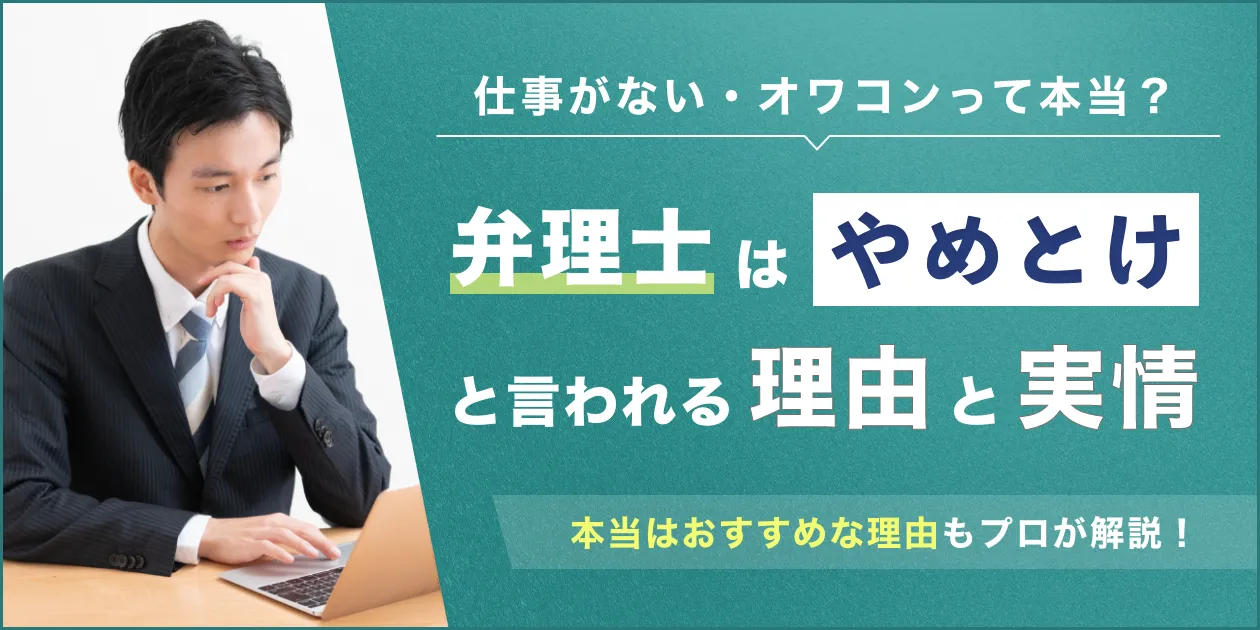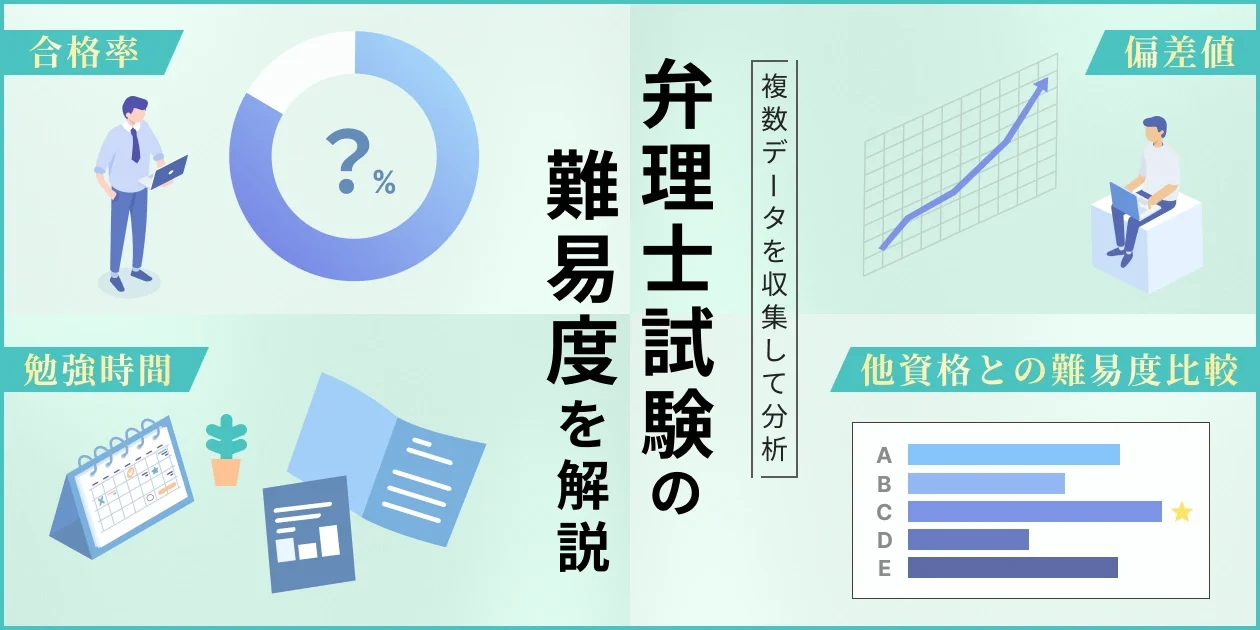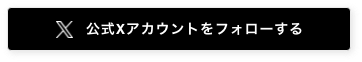【弁理士】退職に必要な手続きや流れ・伝え方やタイミング・注意点

by LEGAL JOB BOARD 三島善太
キャリアアドバイザー
- 担当職種:

こんにちは。弁理士に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の三島です。
今回は、退職を考える弁理士に向けて「退職の流れや必要な手続き」について解説します。
転職・退職の際のご参考としていただけますと幸いです。
▼個別相談を受付中です
この記事の目次
退職の流れ
一般的な退職はこのような流れで行われます。
- 退職する旨を報告する。
- 退職日の相談をする。
- 退職届を提出する。
- 業務の引継ぎを行う。
一つずつ、注意するポイントを解説していきます。
①退職する旨を報告する
退職をするための最初のステップは「退職の報告」です。
退職の報告の際は対面で行うようにしてください。アポを取るのはチャットで構いませんが、正式な退職の報告なので面と向かって退職理由を伝えましょう。円満退職とする場合は、対面での報告が好ましいからです。
退職する旨を伝えるにあたって、気をつけるポイントが2つあります。「報告のタイミング」と「退職理由」です。
報告のタイミング
退職を伝えるタイミングは「次に働く事務所の内定が出た時」がベストです。
次の職場の内定が出ていないまま退職することも可能ですが、転職活動がスムーズにいかないリスクを考えると、慎重になった方が良いでしょう。
またここで注意していただきたいのは、「退職日と次の職場の初出社日が被らないようにすること」です。
次の職場の内定が出たとき、「初出社の日程」のお話が出ますが、その際に「退職できる日程」を考慮して回答しないと、初出社の日になっても前事務所に在籍している状態になる恐れがあります。
そのため、退職する際は「今の職場は何日前に退職を申し出る必要があるか」を調べ、そこから逆算して「次の職場の初出社日を決める」ようにしましょう。
法律上では、退職する14日前には退職の報告をする必要がありますが、職場によっては「雇用されたときの条件」によって決まっているので、今の職場の雇用契約書を見て調べておきましょう。
たまに「法律上では14日前の報告で良いことになっているから、14日前に報告しよう」と考える方がいらっしゃいますが、「円満退職」をするためには、できる限り「事務所のルールに従って辞める」ことを推奨します。
退職理由・伝え方
退職の意思を伝えるときは、理由があるとスムーズに話を進めやすいです。
たとえば以下のような言い回しです。
- クライアントの幅を広げるため
- 家族の転勤のため
- 自身のスキルアップのため
- 独立を考えているため
いろいろ理由があると思いますので、その理由も添えて、メールや口頭でお伝えしましょう。
「給料が低いから」「残業が多いから」といった「待遇面」の理由を一番の主張としてしまうと、スムーズな退職が難しくなる恐れがあります。
退職に至る一番の理由がたとえ「待遇面」であったとしても、それをストレートに伝えることは控えましょう。
またそういった理由を伝えると「給料を上げればいてくれるのか」「残業を減らせば退職を取り消してくれるのか」といったような引き留めに合う可能性も出てきます。
事務所側も納得する理由があればしっかりと向き合ってくれるのです。
②退職日の相談をする
次は「退職日の相談をする」際の注意点についてです。
事務所の就業規則を確認し、自分の持っているプロジェクトなども考慮した上で退職日を指定しましょう。
現在の業務状況によっては、退職日が「3ヶ月後」「半年後」となるケースも珍しくありません。事務所によっては「年度末まで」と指定される場合もあります。
ただし、あなたの都合もありますので、事務所側の条件を一方的に受けるのではなく、あくまで話し合いを交わしながらお互いにとってベストとなる日程を調整しましょう。
稀に「あなたの代わりとなる、次の人の採用が決まってから」と言われることがあります。この場合は日程が決まらないため、あくまで「今月末まで」「〇月〇日まで」というふうに、退職日を明確に決めるようにしましょう。
ちなみに、内定先(次の職場)に伝えた初出勤日と、実際に働ける日があまりにも違いすぎると内定が取り消される場合があります。
面接での印象を良くしようと早すぎる日程を伝えてしまうと、後のトラブルになりかねます。現実的な日程で答えられるように下調べをしておきましょう(過去に辞めた人に聞く、就業規則を見直すなど)。
③退職届を提出する(テンプレートあり)
退職日が決まったら退職届を提出します。
▼退職届のテンプレートをダウンロードしたい方はこちら(PCからのみダウンロード可)
退職届はパソコンでも、手書きでもどちらでも構いません。
以下の画像は、退職届のサンプルです。

退職届作成のルールは下記になります。
【用紙】
- サイズはB5もしくはA4
- 白を使用。手書きの場合は、白便箋を使用し罫線があるものを使用する場合はシンプルなものを選択
【封筒】
- 白地で、郵便番号枠・柄が無い無地を使用
- サイズはB5用紙であれば《長形4号》で、A4用紙は《長形3号》
【ペン】
- パソコン、手書きのどちらの場合も黒インクや黒ボールペン・万年筆を使用
- 油性、水性どちらでもOK
①冒頭:《退職届》と記載
②導入文:一行目下部に『私儀』または『私事』と記載
③退職理由:自己都合の場合『一身上の都合』と記載、会社都合の場合は『退職勧奨に伴い』など具体的に記載
④日付:上司と決定した年月日を記載
⑤氏名:正式な所属部署名、氏名はフルネームで記載。氏名の下に捺印が必要
⑥宛名:所属事務所の所長宛。敬称は”殿”もしくは”様”。役名とフルネームを記載。自身の名前よりも上方に書く。
下記にテンプレートをご用意いたしましたので、ぜひご活用ください。
※PCからのみダウンロード可
④業務の引継ぎをする
退職が決まれば業務の引継ぎをおこないますが、何かトラブルが起これば対応できるよう、余裕のあるスケジュールで進めましょう。退職の3日前までに引継ぎが終わるとベストです。
引継ぎ内容は形が残るよう書面にまとめ、後任者が困ったとき内容を確認できるようにします。
引き継ぐ内容は下記のような内容が理想です。
- 業務内容・進捗状況・優先順位など
- 発生したことのあるイレギュラーやトラブルの対策と経緯
- 業務、案件の目的や社内の位置づけ
よく使う資料がある場所などを明記しておくと、より親切です。
また、この期間にクライアントに退職の旨を伝えるようにしましょう。自身がメインで対応していたクライアントには、特に伝えておいた方が良いかと思います。
円満退社のためのポイント
無理やり辞めたり、揉めて辞めたりしないようできる限り円満退職を目指しましょう。
弁理士業界は狭い世界なので、転職先の所員様と前職の所員様が仲良くしている・つながっているケースも珍しくありません。
例えばですが、辞めたときの印象があまり良くなく、前職の方が次の職場の方に、自身に不利になるような噂を流したりしてしまうなど、そういったケースもあるかもしれません。
そうすると転職先でのイメージダウンにつながり、精神的にきつくなってしまいます。いつ、どこで前職の方と会っても大丈夫なよう、円満退職をとにかく意識しましょう。
事務所の就業規則を守る
法律で定められているものとは別で、就業規則は事務所や会社によって変わります。
いくら法律には反していないからと言って、就業規則を破ることは基本的に避けたいですよね。
円満退社のためにも就業規則はしっかり見直し、それらを踏まえた上で転職をしましょう。
引継ぎを完璧にする
引継ぎが完璧に行われていないと、事務所側にかなり迷惑をかけてしまします。引継ぎに抜けがある、未完了のまま転職してしまうことは無いように心がけてください。
退職・転職の際はスケジュール管理が非常に大切です。辞めたときの印象が悪くならないようにするために、余裕を持って引き継げるようにしましょう。
クライアントの引き抜きは注意
独立をする方は、クライアントの引き抜きを行うと、退職予定の事務所からあまり良くない印象を持たれる恐れがあります。
クライアントを引き継ぐ場合は、所長と十分に話し合うことが大切です。そして、独立した事務所で自身のクライアントを対応してもいいかとお伺いを立てておく必要があります。
独立後は所長同士として協力し合える関係でいることが、知財業界で活躍する為にはベストです。
転職の流れ・注意点
退職をスムーズに行うためには、次で働く職場から前もって内定をもらっておくことが大切だと前述しました。
内定承諾までの流れとしては以下になります。
- 情報収集を始める、キャリアアドバイザーに登録をする
- 気になる事務所の求人を探し、応募する
- 書類審査を通ったら、試験や面接、プレゼンテーションなど(事務所によって異なる)
- 最終面接
- 内定を貰う
- 内定承諾(1、2週間程度)
①〜⑥までが主な転職の流れになります。
働きながら転職先を探すのは大きな労力を要します。そこで非常に便利なのが「転職キャリアアドバイザーサービス」です。
転職キャリアアドバイザーサイトに登録し、あなたの希望年収、許容できる残業時間、希望する業務などをキャリアアドバイザーに伝えると、それにマッチした求人を定期的に紹介してくれます。
自分で求人を探す手間が省けるので、効率よく転職活動が行えます。
転職活動を始めるベストなタイミング
「本格的に転職活動を始める1~2ヶ月前」から、転職キャリアアドバイザーに登録するのがベストです。
前もって転職キャリアアドバイザーに登録しておくことで、あなたの希望に合った求人が定期的にあなたの元に届くことになります。
そうすると、実際に転職を始めようとした時に「すぐに」求人に応募できます。
求人に応募するには「サイトへの登録」「履歴書や職務経歴書の作成」などの事前準備が必要となりますが、前もって登録しておけば事前準備を済ませられるので、推奨します。
働きやすい職場に出会うために
次の職場は、早期退職することなく、長く働きたいものですよね。そうするためには、「長く働けるくらい良好な職場環境」である必要があります。
そんな職場に出会うためには、弁理士業界の職場情報を常日頃から収集しなくてはなりません。
そのためには、求人を見比べたり、知り合いの弁理士に聞いたり、ネットの口コミを調べたり…などなど、細かいリサーチが必要となります。
しかし、これらを一人で行うのは大変です。こういった場合も、転職キャリアアドバイザーに登録すればすべてキャリアアドバイザーが代行してリサーチしてくれます。
また、個人によるリサーチは「情報の偏りや正確性」にも少し問題があるものです。というのも、自分で見た求人情報や、知り合いやネットで得た職場口コミは、実は間違っていたというのがよくあるケースだからです。
例えばよく聞くケースが、「知人の紹介で入ったのはいいものの、想像していた職場とは違っていた。でも、紹介してもらった立場で辞めづらい」といったエピソードです。
他にも、「求人には残業が少ないと書いてあったのに、実際に入職したら残業はおろか土日出勤も強いられている」というケースもあります。
転職キャリアアドバイザーは、以上のような情報格差を解消するために存在しています。中立的な立場からより正確な情報を得たいと思う方は、キャリアアドバイザーの活用を推奨します。
複数の求人を受けたい場合の注意点
希望する転職先が複数ある場合、一つの職場から内定を受け取ったあと、「他の求人の選考も受けてから、どの職場の内定を受諾するか判断したい」という場合が訪れます。
このような場合、選考スケジュールの組み方を誤ると、複数の選考先を天秤にかけられなくなる恐れがあります。
「A社から内定が出たけど、B社も気になる。でもA社は内定承諾の期限は1週間。B社の選考は1ヶ月後だから、B社を受けるならA社を諦めざるを得ない..」
例えばこのようなケースですね。
大きい事務所や大企業の場合、内定承諾の期限は1~2週間程度です。
人気の事務所だと次から次へと応募が来るため、内定を受諾するまでに時間をかけすぎると「じゃあ違う人を採用するので、内定は取り消します」と言われることも。
そのため、複数の求人を受ける場合は「いかに選考日程をうまくスケジューリングするか」が鍵を握ります。
しかし、現職での業務をこなしながら選考を受け、スケジュール管理まで調整するのは非常に難しいです。こういった場合も、弊社の転職キャリアアドバイザーにお任せください。
弊社ではキャリアアドバイザーの方で、選考日程のスケジュール管理を代わりに行います。複数の求人を応募したい場合は、そのことも踏まえた上でスケジューリングするので、漏れなく選考を受け、求人を比較することができます。
ブラック事務所の見分け方
転職するのであれば、「ブラック事務所」は絶対に避けたいところですよね。
大手で名の知れた事務所・企業だからといって教育体制が整ってるとは限りません。ブラック事務所とは表面だけでは分からないのです。
そこで、ブラック特許事務所を避けるための方法を以下の記事でまとめました。
また、上記以外でも「ブラック事務所の避け方」はいくつかあります。以下で解説します。
弁理士同士の情報交換を有効活用する
知り合いの弁理士や、同期の弁理士での意見交換はかなり有効な手段です。弁理士会などで他の弁理士と交流する場合は、職場の評判や口コミについて情報交換していくと良いかもしれません。
しかし、その情報も100%正しいものだとは言い切れないので注意が必要です。
例えば、自分が感じる残業量の『多い』と、知り合いの方の『多い』が必ずしも同じでは無いように、中立性に欠ける場合があります。具体的な情報交換を心がけましょう。
ネットで事務所の口コミを見る
ネットでの口コミサイトなどをよく見かけますが、それも1つの情報収集手段といえます。多少信憑性には欠けますが、全てが嘘の情報というわけでは無いでしょう。
結構多いのが、同じ事務所だけれども違う職種の方のレビューを参考にしているケースです。同じ事務所でも、職種が違えば業務内容、給与形態、残業量なども違ってきます。
ネットの口コミを見る際は、職種や働いている期間なども考慮するようにしましょう。
ブラック事務所を避けたいなら転職キャリアアドバイザーを活用
ブラック企業という言葉がかなり浸透し、士業の世界も徐々に変わり始めています。しかし、時々ブラックという言葉が一人歩きしているように感じる時があります。
業務内容にやりがいを感じ、クライアントファーストで動く事務所。チャレンジングなことに取り組んでいる事務所。残業が多くてもしっかり手当てが出て、仕事にやりがいを感じる職場も中にはあります。このような事務所は、一概にブラック事務所とは言えません。
「残業代が支払われない」「上司からのパワハラがすごい」といった事務所はブラック事務所です。
弁理士・知財専門の転職キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」は、トップクラスの特許事務所の求人数を誇ります。
求人票では分からない特許事務所の評判や口コミ、裏事情など、良いことも良くないことも、キャリアアドバイザーから話を聞くことができます。
また、リーガルジョブボードでは、ブラックな特許事務所はご紹介いたしません。
特許事務所への転職で少しでもお悩みの方は、弁理士・知財専門キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」にご相談ください。
キャリアアドバイザー利用のメリット